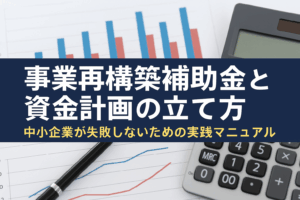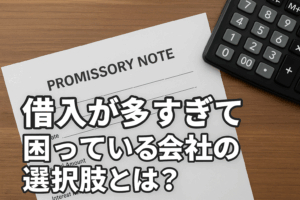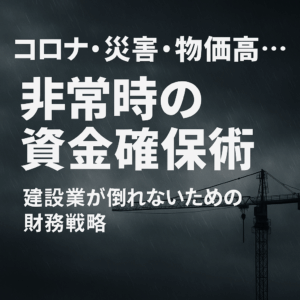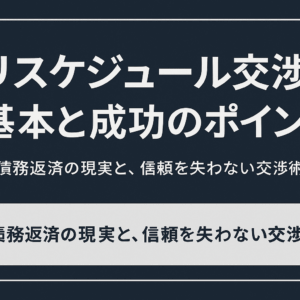経営改善計画書の書き方と再生支援機関の活用法 4
2025年9月4日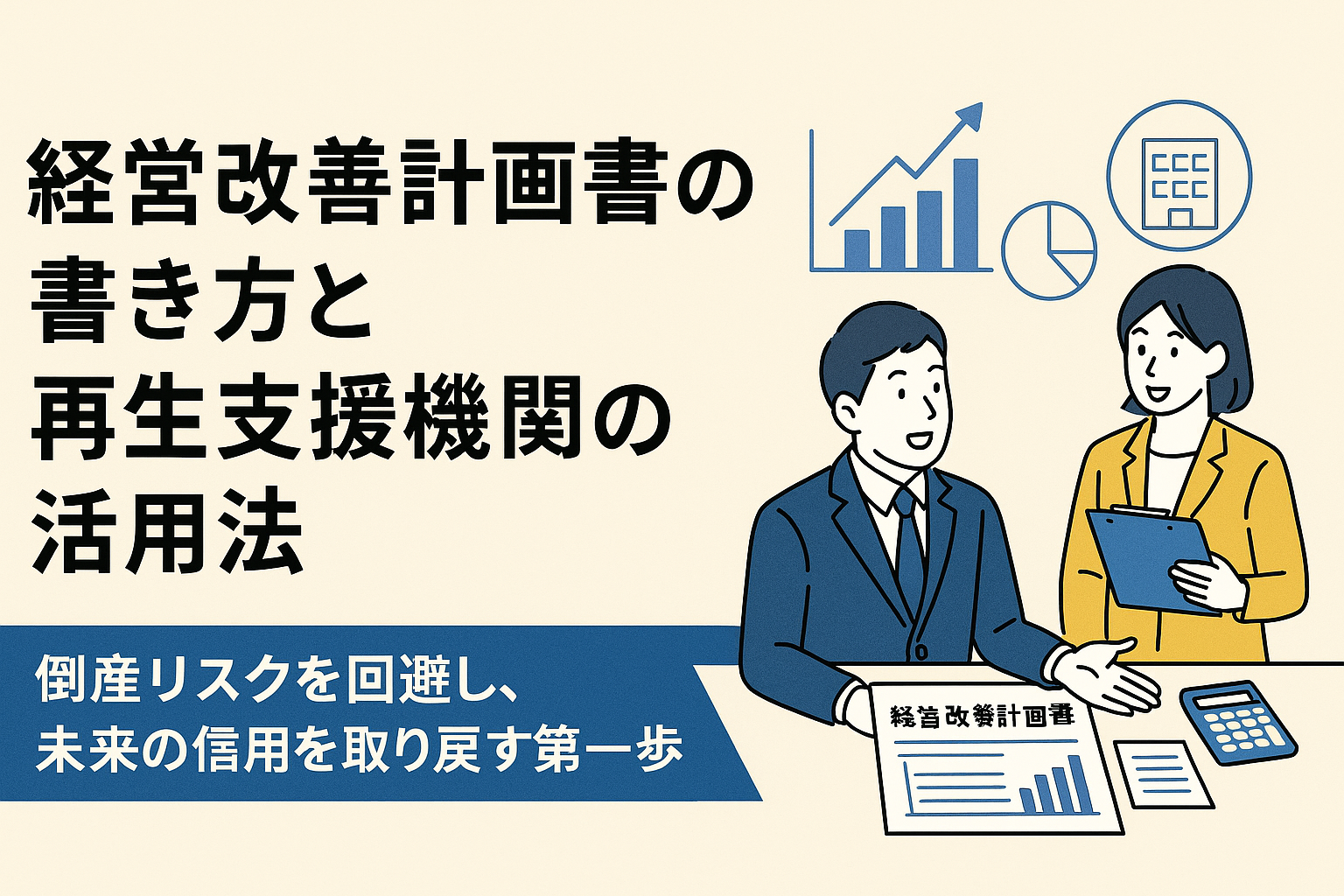
経営改善計画書の書き方と再生支援機関の活用法
― 倒産リスクを回避し、未来の信用を取り戻す第一歩 ―
はじめに
資金繰りが厳しい、金融機関との関係が悪化している、今後の経営に不安がある── そうした中小企業にとって、「経営改善計画書」の策定と「再生支援機関」の活用は、経営再建への希望となる選択肢です。
本記事では、再生支援の現場で数多くの経営者を支えてきた視点から、
● 経営改善計画書の基本構成と書き方
● 国の認定を受けた支援機関の活用法
をわかりやすく解説します。
第1章:経営改善計画書とは?
「計画」ではなく「再生の約束」
経営改善計画書とは、財務・営業・組織など企業全体を見直し、3〜5年かけて経営状態を立て直す計画をまとめた文書です。
金融機関にとっては「今の融資を継続してよいか」を判断する重要な資料であり、
経営者にとっては「再起を懸けた再生の約束」ともいえる存在です。
第2章:経営改善計画書の基本構成
- 会社概要・沿革
- 現状分析(経営課題の明確化)
- 数値分析(損益・資金繰り・財務状態の可視化)
- 再建方針(事業戦略・収益モデルの見直し)
- 具体策(コスト削減・人員体制・販売戦略など)
- 数値計画(損益予測・資金繰り予測)
- モニタリング・PDCAの実施体制
この「構造」をもとに、金融機関に「再生できる見込みがある」と納得してもらうための“筋の通った計画”を描くことが鍵です。
第3章:計画書作成のポイント5選
- 「なぜ苦しいのか」を数字で示す
貸借対照表・損益計算書・資金繰り表を活用し、原因を特定。 - 改善策は「行動ベース」で記述する
「売上アップ」ではなく「新規顧客を月3社獲得」など定量化。 - 「自助努力」の姿勢を見せる
経営者の報酬カット・資産売却なども評価対象に。 - 金融支援の内容は“筋を通す”
リスケ・追加融資の根拠を丁寧に説明。 - 第三者支援の存在を明記する
認定支援機関・税理士・コンサル等が関与している旨を記載。
第4章:認定支援機関・再生支援協議会の活用法
● 認定経営革新等支援機関とは?
国が認定した、経営改善・資金繰り・再生計画の支援実績を持つ専門家(税理士・中小企業診断士・コンサル等)です。
計画書の策定支援を受けることで、精度が上がり、金融機関の信頼も得やすくなります。
● 再生支援協議会(中小企業再生支援協議会)とは?
国の制度の一環として、都道府県ごとに設置されている中立的な支援機関。
複数の金融機関や保証協会との調整や、ハードな再生計画の策定支援を行います。
● 活用するメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 第三者の客観性 | 金融機関との信頼性が向上 |
| 補助金活用 | 「経営改善計画策定支援事業」の対象になれば費用の2/3補助 |
| 多方面の交渉支援 | リスケ調整・追加融資なども専門家が支援 |
第5章:支援を受けるまでの流れ
- 現状把握・相談(初回ヒアリング)
- 計画書のドラフト作成(支援機関と共同作業)
- 金融機関への説明・交渉
- 計画合意・モニタリング開始
※相談段階で“リスケ前提”ではなく、あくまで「再建のための協力依頼」であることが重要です。
第6章:よくある失敗と成功事例
❌ 失敗例:自己流で作って信用されない
Excelで表だけ作成 → 金融機関「これは計画ではない」と却下。
⭕ 成功例:認定支援機関を通じて提出
数字の整合性・改善策の実効性が評価され、条件変更がスムーズに。
おわりに|再建に“必要なのは勇気”と“伴走者”
経営改善計画書は「未来の信用を再構築するための設計図」です。
再生支援機関というプロの伴走者を得ることで、あなたの経営再建は確実に前進します。
経営再建の第一歩、共に歩みませんか?
エスエスコンサルティングでは、経営改善計画書の策定から
▶ 無料相談はこちら
金融機関との交渉支援、認定支援機関の連携までフルサポートします。