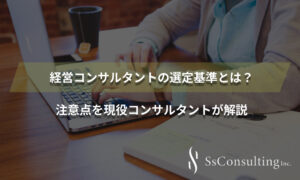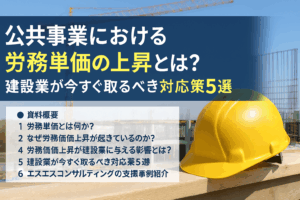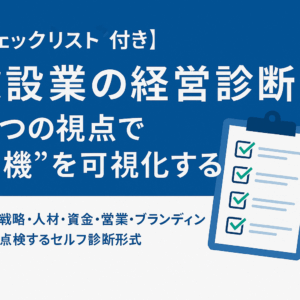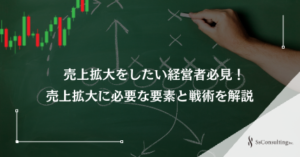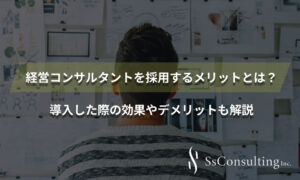中小企業の経営者が必ず覚えておきたい資金調達の方法とメリット・デメリットを徹底解説!
2022年11月7日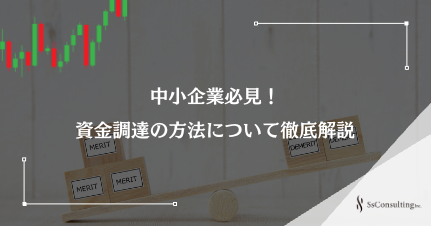
「私財を投入して経営してきたけれど、もっと事業の規模を大きくしたい」
「自己資金だけでは足りなくなってきた。資金調達をしたい」
このように考えている中小企業の経営者も少なくないでしょう。
中小企業にとって、経営初期の大きなハードルのひとつが資金調達です。
中小企業が資金調達を考えるにあたって、まず大事なことはどんな選択肢があるのかを知っておくことです。
資金が必要になった際に慌てないためにも、資金調達に関する基礎知識を身につけたいところ。
本記事では、資金調達の方法ごとに、その特徴とメリット・デメリットを徹底解説していきます。
資金調達の前に覚えておきたい資金の種類

ここからは、まず資金調達の前におさえておきたいポイントとして、資金の種類について説明します。
経営資金には大きく分けて、「自己資本」と「他人資本」の2つがあります。
それぞれの特徴とメリット・デメリットについて以下で詳しく見ていきます。
自己資本
自己資本は株主資本とも呼ばれ、株主が出資した資本金や企業が積み上げた繰越利益などを指し、企業が安定した経営をするために必要な資金(資本)のうち、返済する必要がない資金です。
自己資本は新たに株式を発行すること(増資といいます)や、利益を積み上げていくことで増やしていくことができます。
メリット
自己資本を増やすメリットは、上述の通り返済する必要がないことです。
減資(株式の消却)をしたり、繰越損失を出さない限り、自己資本が外部に逃げていくことはありません。
信用度の点で借入や社債発行が出来ない企業であっても株式の発行は可能です。
このように長期間にわたって安定的に資金調達できる点もメリットと言えます。
また、経営の初期段階においては、投資家に出資してもらうことで相談などにも乗ってもらえることがあります。
デメリット
自己資本を増やすデメリットは2つあります。
まずは、大口の投資家や投資企業に経営権を握られてしまうリスクが考えられます。
いわゆる「物言う株主」です。
これら物言う株主の意志も尊重しながら経営していく必要が出てきます。
そのため、投資家から出資を募る場合は経営者(経営陣)だけの意志で経営していくことが難しくなります。
次に、株主に対して配当金を支払う必要があることです。
配当金を出さないという戦略も可能ではありますが、低金利が続く昨今の日本では、高配当の株式が投資家に好まれ、逆に配当金が少ない企業には投資家が付きづらい傾向があります。
自己資本には返済義務はないものの、株主が要求する見返り(専門用語で資本コストと言います)を考慮すると、後述で紹介する他人資本よりも高コストになる場合もあります。
他人資本
他人資本とは、将来返済する必要のある資金のことで、具体的には借入金や社債を指します。
他人資本は、金融機関から借入を起こしたり、社債を発行することで増やしていけます。
メリット
他人資本を増やすメリットは主に3つあります。
まずは、投資家探しと比較して難易度が低いことです。
金融機関等に資金が必要になったタイミングで相談に行くことで、必要な手続きはあるものの比較的簡単に資金調達が可能です。
そのため、自己資本の場合に投資家を募る必要があるのと比べて、素早い資金調達ができます。
もうひとつは、レバレッジ効果です。
レバレッジとは「てこ」のことで、少ない自己資金(自己資本)から大きな利益を上げられるという意味です。
たとえば、自己資本が1,000万円の企業でも、500万円の他人資本があれば、1,000 + 500で1,500万円まで設備投資が可能になります。
一般的には設備投資が大きい方が、もたらされる利益も大きいので、資金効率(自己資本と利益の割合)は改善します。
これがレバレッジ効果です。
さらに、資本コストが安いことも挙げられます。
他人資本の資本コストとは、借入先へ支払う金利を指しますが、これは株主へ支払う配当等の資本コストよりも安い場合がほとんどです。
低金利が続く現代の日本では、より当てはまります。
デメリット
他人資本における唯一最大のデメリットは、返済義務があることです。
会社の業績に関係なく返済期日が来たら、耳を揃えて元本と利息を支払わねばなりません。
レバレッジを掛けたビジネスが想定通りの利益を上げられなければ、返済が滞り、最悪の場合倒産もあり得ます。
このようなことを防ぐためには、事前にビジネスプランや返済計画を、借入先とも共有しつつしっかり固めておくことが必要です。
監修コメント
| 創業当時は金なし、コネなしで事業を進める方は多い思います現実的な話をすると政策金融公庫の創業融資は審査が通りやすいです。しかし、返済保証人が代表者本人になるので融資もよくよく検討をしていくと良いです。 |
資金調達する前に経営者が確認しておくべきこと

ここからは、実際に資金調達をする前に経営者が確認しておくべき事項を紹介します。
自己資本・他人資本のデメリットの項とも重複する内容がありますが、重要なポイントなのでしっかり押さえておくようにしましょう。
具体的にはこちらの四点です。
- 融資の場合に返済できるかどうか
- 資金調達が社内の総意であるかどうか
- 家族の同意が取れているかどうか
- 投資されるデメリットを理解しているか
以下で詳しく見ていきます。
融資の場合に返済できるかどうか
他人資本(融資)は、最もシンプルな資金調達ですが、返済義務という唯一最大のデメリットがあることは上述の通りです。
特に過去の実績が少ないうちは、将来どのくらいの利益を上げられるのか、そのうちどのくらいを返済に回せるのか、これらは予測の範囲を出ません。
予期しなかったトラブルや災害、外部環境の変化で返済が滞ってしまったら、最悪の場合倒産が待っています。
そうならないためにも、実現可能性の高い事業計画・収支計算書を立案し実行していくことが重要です。
資金調達が社内の総意であるかどうか
上述の通り、融資には返済が滞るリスクがあり、増資には出資者に経営権を握られてしまうリスクがあります。
そのため、社内でリスクとメリットを天秤にかけ、総意として資金調達を選択することが重要です。
融資を受けた後に、「あの融資には反対だった」と社内で議論になるのは絶対に避けなければなりません。
家族の同意が取れているかどうか
融資を受ける場合、金融機関は基本的には経営の健全性や事業計画を見ますが、同時に経営者の個人資産も審査の計算に入れることがあります。
場合によっては、経営者が保証人や連帯保証人になることを融資の条件にされる可能性もあります。
このような場合、返済が滞ってしまうと経営者やその家族の生活に差し障ることになります。
そのため、融資を受ける前には、社内の経営陣だけでなく、経営陣の家族にも同意を取りましょう。
投資されるデメリットを理解しているか
自己資本、つまり投資を募ると、投資家や投資企業に経営権を握られてしまうリスクがあります。
また、他人資本、つまり融資を受けると、借入先の金融機関等が経営に口を出してきたり、関連会社のサービスを押し付けてくる場合もあるようです。
このように自己資本・他人資本いずれも投資されるデメリット・リスクが存在します。
これらのデメリットを理解した上で資金調達を行うことが重要です。
監修コメント
| 法人格ですので社内会議等、家族会議等も必要ではありますが経営者たるもの潤沢な資金で経営をしたいと思います。しかし、借入にはリスクがあるため前向きな融資、後ろ向きな融資、融資にも色々とあります。経営者として責任の持てる範囲で資金調達することをお勧めします。何故なら全責任は経営者本人だからです。 |
経営者が覚えておきたい資金調達の方法

ここからは、資金調達の方法について、自己資本・他人資本両方にわたって紹介していきます。
- 金融機関借入
- 各種補助金
- 投資家
大きく分けて上記の3種類です。
以下で詳しく見ていきます。
金融機関借入
まずは、金融機関からの借入について説明します。
収支計算書や事業計画を示して審査してもらうというプロセスは共通していますが、金融機関の種類によって特徴があるので、それぞれの金融機関について以下で説明します。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、日本政府が100%出資している金融機関です。
日本経済活性化や生活の質の向上を目指して活動していて、一般の民間企業とは異なる経営を行っています。
日本政策金融公庫には、さまざまな融資制度があります。
対象者や企業状況によって、利率や融資の限度額が異なるため、自社に最も適した融資制度を選択するようにしましょう。
日本政策金融公庫の融資制度には、下記のようなものがあります。
・普通貸付
事業を営むほとんどの人が対象で、上限は4,800万円(特別設備資金7,200万円)
・経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)
売上減少などで経営状態が悪化している事業者が対象で、上限は4,800万円
・新規開業資金
起業する方か、起業後おおむね7年以内の方が対象で、上限は7,200万円(うち運転資金は4,800万円まで)
・女性、若者/シニア起業家支援資金
起業もしくは起業後おおむね7年以内で、女性や35歳未満の方、55歳以上の方が対象で、上限は7,200万円(うち運転資金は4,800万円まで)
また、中小企業向けには、このほか、融資上限が高い長期事業資金貸付制度も用意されています。
銀行
銀行には、メガバンク3行のほか、りそな銀行などの都市銀行と、各地の地元に根ざした地方銀行、ネット銀行など多様な種類があります。
基本的には融資の担当に連絡して事業計画や収支計算書を示し、融資を受けることになります。
事業の健全性をわかってもらう資料を用意することと、資金の用途を明確にすることが重要です。判断のための多くの情報を提供する必要があり、銀行の融資担当の方と積極的にコミュニケーションも必要になってくるでしょう。
そうして決定した金利は自社の信用度が高い(経営が安定している)ほど安くなります。
また、一般的にはネット銀行のほうが金利が安い傾向があります。
一般的に中小企業や個人事業主は大企業に比べて信用を得にくいという現実があります。
昨今、大企業と中小企業のファイナンス格差は拡大する一方です。
このような厳しい状況下で融資を受けるためには、入念な事前準備が重要になってきます。
信用金庫
信用金庫とは、地方銀行よりも地域に密着し、地域住民や中小零細企業を支援する金融機関で、地域住民や中小企業からの出資で運営しています。
また、信用金庫は「信用金庫法」に基づき運営しています。
代表的な制限が融資先の制限で、原則として信用金庫の所在地域の中小企業(従業員数300人以下または資本金9億円以下)が対象です。
経営初期段階の経営者の中には、金融機関で融資を受けるには1,000万円を超える金額でないと取扱いをしてくれないといったイメージが先行しており、どの金融機関を選べばよいのか迷う方がたくさんいます。
信用金庫は中小零細企業を専門としていますので、取扱い融資金額も1,000万円以下であることが多いことから、数百万円規模の比較的小規模に事業を起こしたい方にはおすすめの金融機関です。
クレジットカード会社
クレジットカード会社も中小企業の借入先になりえます。
法人クレジットカード(法人カード)を発行しているクレジットカード会社も多いので、この法人カードを使って資金調達していくことになります。
法人カードは、個人カードと違い決済枠が数百万円から1,000万円程度と大きく、また支払期限も最大3ヶ月程度まで伸ばせることがあるため、資金繰りに大きな影響があります。
また、取引をデータ化してシステムに取り込めることや、ポイントが付くことなどは一般的な個人カードと同様で、この使い勝手の良さもクレジットカード会社のメリットです。
創業補助金
創業補助金は、「これから事業を始めようとする企業」や、「起業して間もない企業」が利用できる制度です。
この補助金は、借入とは異なり、返済する必要のないお金です。
創業補助金の金額や申請方法、申請期間などは、その年によって異なります。
これから起業しようとしている方は、起業を予定している年の創業補助金の募集要項についてこまめにチェックしておきましょう。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が、事業の持続的発展に向けて、地域の商工会議所または商工会の支援を受けながら経営計画を作成し、この経営計画の実行に必要な販路開拓などの取組みに要する経費の一部を補助するものです。
こちらも返済義務はありませんので、経営初期段階の中小企業には頼もしい存在です。
個人投資家
個人投資家というのは、その名のとおり、創業間もない企業や小規模な事業者などに投資する個人のことです。
通常、起業しようというタイミングで個人投資家に目を向けてもらえることは多くありません。
ほとんどの場合、事業展開をしていく中で個人投資家の目にとまって融資や出資を受けられることになります。
そのため、まずは優れた事業計画を立てたり、投資家の目にとまるユニークな事業展開を行ったりする必要があるでしょう。
ベンチャーキャピタル(VC)
ベンチャーキャピタル(VC)とは、成長の可能性が高いベンチャービジネスに対する投資を主な業務とする企業です。
投資した起業が成長することによる利益、つまり株式上場やM&Aによりキャピタルゲイン獲得が見込める出資のみを行います。
創業間もなく、今後どのような事業をしていくのか明確でない企業や、大きな成長が見込めない企業に対して投資をする可能性は低いでしょう。
ベンチャーキャピタルから投資を引き出すためには、優れた事業計画や事業展開の展望があり、資金を受けることで事業成功ができるというアピールをする必要があります。
監修コメント
| 借入機関も様々にあります。ありますがそうは簡単に融資には応じてはくれません。その辺を踏まえ、仮に各機関が融資をしてくれたと仮定します。その際に必ず事業が成功しなければ、返済はできません。返済できなければ借入したところに返済ができないことから迷惑がかかります。そのため、綿密な事業計画を立て幹部社員もそれならいけるという形で借りるべきです。 |
資金調達する前に経営者がすべき準備
ここからは、実際に資金調達をする前に経営者がすべき準備について説明します。
- 各調達元の条件の確認
- 事業計画書の準備
- 収支計算書の準備
以上3点です。
順番に詳しく見ていきましょう。
各調達元の条件の確認
まずは、各調達元の条件の確認です。
借入金であれば、金利はいくらで返済ペースはどうなっているか。
社債であれば、金利・返済ペースに加え証券会社などに支払うエージェント手数料も確認が必要です。
増資であれば、新しい株主が要求する配当金やキャピタルゲインの水準はどのくらいか、株式交付費はどのくらいかかるかを確認しましょう。
補助金を申請する場合は、補助金の対象になっているか、審査を通るために必要な条件は何かを知らねばなりません。
これらをもれなく調査し、並べて比較検討していきましょう。
事業計画書の準備
借入先が決まったら、事業計画書を準備していきます。
説得力のある事業計画書は、融資者・投資家へのプレゼンテーションの質を均一に保つために大きな役割を果たします。
外部に向けた説得以外にも、自分の目指す事業の実現性を客観的に分析する上でも有用で、事業の羅針盤となります。
最近は事業計画書の手引きやテンプレートがインターネット上で多数見つかるので、上手く活用するようにしましょう。
収支計算書の準備
つづいて、収支計算書を準備します。
収支計算書とは、1年間のすべての収入、支出の明細表であり、予算と対比することにより、予算の執行状況を明らかにする書類です。
事業で利益が出ていても、現金が足りないと買掛金や借入金の返済が滞ってしまうリスクがあるため、主に現預金の流れを把握し、投資家や融資者に説明するために作成します。
似た用途の資料として財務諸表の損益計算書がありますが、こちらは利益と損失の状態を示すためのものです。
たとえば、減価償却費は費用ですが、実際には現金の流出はないため、収支計算書には載せません。
このような違いがあるため、損益計算書を作成している場合でも追加で収支計算書を作成するようにしましょう。
収支計算書もテンプレートがインターネット上で多く見つかるので、上手く活用して説得力のある収支計算書を作成しましょう。
監修コメント
| 収支・コスト計画は綿密にするべきです。 全ての数字が頭に入り各幹部社員と共有し月次収支・コスト会議にて社内共有し経営していきましょう。 |
資金調達のメリットとデメリットを理解した上で利用しよう
本記事では、資金調達の方法ごとに、その特徴とメリット・デメリットを解説してきました。
- 資金調達方法には自己資本と他人資本があり、それぞれにメリット・デメリットがある
- 特にデメリットをしっかり意識した上で、経営陣・家族の同意の元資金調達をすべき
- 資金調達先にも種類があり、それぞれの特徴がある
事業を運営・拡大していく上で資金繰りに関する問題は避けて通れない道ですが、一方でなかなか相談相手がいない話題でもあります。
それぞれの方法によって、返済の要不要や期間、利率などが大きく異なるため、自社に最も有利な方法を選ぶようにしましょう。