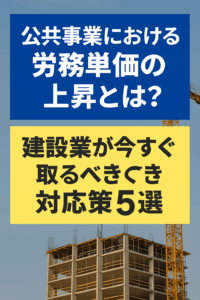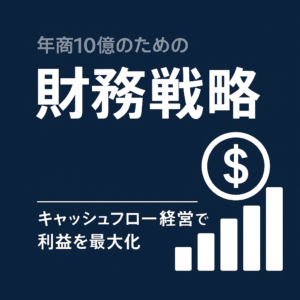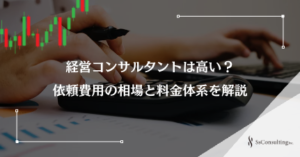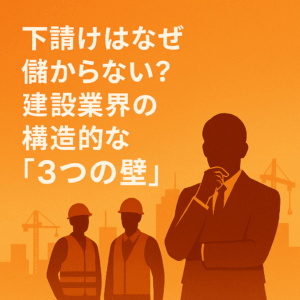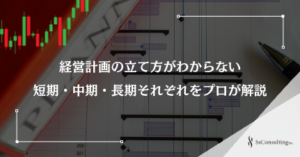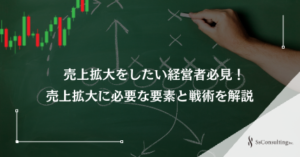経営者が事業展開を考えるときに必要な知識を解説!方法や当社成功事例も併せて紹介
2022年11月18日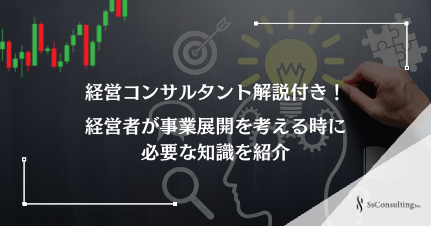
規模を問わず、企業が持続的に成長していくためには、新規事業に取り組む必要性があります。
経営者の方々は、事業拡大における戦略の立て方やその考え方などをしっかりと頭に入れておく必要があります。
そこで本記事では、事業展開の考え方や戦略、経営計画の作成方法を解説します。
事業展開について

事業展開とは、企業が新たな分野で事業を開拓する(立ち上げる)ことです。
もしくは既存のビジネスを拡張し、スキーム含め領域を広げる取り組みを指します。
前者の場合、たとえばシステム開発会社が新たにゲーム事業に乗り出すといった話が当てはまります。
また、後者での典型的な例を挙げるならば、本国以外への進出が挙げられます。
日本で飲食事業を営んでいた会社が他の国に店舗を構えるケースなどはよく見聞きするものです。
テクノロジーの発展によって、事業環境が刻一刻と変化を遂げる昨今。
現状維持では心許ない経営者の方も少なくないでしょう。
実際、過去の実績にあぐらをかいていては、あっという間に競争に取り残されてしまうおそれがあります。
自社ビジネスがいつ淘汰されるか分からない時代にいるということは避けられない事実です。
ただし、動くにせよ闇雲であってはいけません。
事業展開を検討するに際しては、まず理由を明確にしておきましょう。
後々行き詰まったとき、原点(事業展開の理由)に立ち返ることができれば、再出発のモチベーションにもつながるでしょう。いうなれば(事業展開の)本質的な意味もそこに含まれます。
事業展開は企業が成長し生き残るために不可欠な戦略であるため、経営者は事業展開の戦略・考え方について理解を深めておくことが大切です。
監修コメント
| 昨今、ビジネスは目まぐるしく変化をしていますネット上では昨日のことが古くなったり良い口コミも悪い口コミも早いのが今のビジネスの動きです。 自社の得意分野から新事業実施すにあたりビジネスの本質を外れては意味がないと思います。 最も、得意な分野でビジネスができるよう綿密なリサーチをし社員と共に歩めるようにすると良いでしょう。 |
経営者が行うべき事業展開の計画の立て方

ここからは、経営者が行うべき事業展開の計画立案の方法について、いくつかのトピックを元に紹介していきます。
- 何をしたいのかの案出しをする
- 事業展開の人材選定をする
- 具体的な戦略会議をして実施可能か検討する
- 展開したい事業含めて経営計画を策定
- 市場調査をして勝てる事業化を判断する
上記5点になります。
順番に詳しく見ていきましょう。
何をしたいのかの案出しをする
まずは案出しをしていきます。
ブレインストーミングのつもりで、少しでも可能性がありそうな事業をどんどん列挙していきましょう。
細かい実現可能性はいったん横において、どんどん数を出すのが重要です。
実施可能性・実現可能性については、別のプロセスで検討していきます。
その点については後述します。
事業展開の人材選定をする
つづいて、事業展開にアサインする人材を選定しましょう。
新たに手掛ける事業に精通するメンバーがいるかというスキルセット(保有スキル)はもちろんのこと、既存のプロジェクトとの繁忙期・閑散期の兼ね合いの調整も必要です。
人材が足りないようであれば、外部から採用してくる動きも必要になってきます。
さらに、しっかりと進捗管理を行うためにも、プロジェクトマネジメント経験のあるリーダークラスの人材を1人はアサインできると、盤石なチームが出来上がります。
具体的な戦略会議をして実施可能か検討する
案出し・人材選定が終わったら、さっそくチームメンバーで戦略会議をしましょう。
ヒト・モノ・カネの観点から、前プロセスで出したアイディアに対して実施可能性を検証していきましょう。
改めて事業展開のビジョンや計画をメンバー全員で共有し、戦略のブラッシュアップや仮説に対する答え、方向性、手配、手段、マニュアル、ロールモデル設定…等々を導き出しながら、皆が納得できる形で落とし込んでいくことが重要です。
また、アイディアをなかなか捻り出せないときは、社内外問わず、成功事例もヒントになり得ます。
過去の成功事例から共通項やうまくいく法則などが抽出できれば、流用するのも一つの手です。
展開したい事業含めて経営計画を策定
策定済みの経営計画に、展開したい事業を織り込んで再策定しましょう。
長期経営計画までは修正の必要はないはずなので、中期経営計画と短期経営計画を修正・再策定していきましょう。
極力具体的な数値を盛り込み、経営の目指す姿、あるべき姿を明確にするのがポイントです。
そのためには定量・定性ともに目的が必要です。
そのうえで、自社のポジショニング、事業展開の有効性、実現性、評価の妥当性を軸に、スケジュールや成長フローなど数値を用いて極力具体的に示すようにしましょう。
経営計画については別の記事で詳しく触れていますので、そちらもご参照ください。
市場調査をして勝てる事業化を判断する
最後に必要なのは、参入する市場の調査をすることです。
市場規模の把握はもちろん、新しい分野の場合は類似する複数の分野から、市場規模を推測する必要があります。
どのような価値を提供し、利益を獲得する方法を明確にするため、市場調査・分析は必ずやっておく必要があります。
また、競合がどの程度あるのかも把握しておきましょう。
監修コメント
| 成功事例を参考にするのもよいと思います。失敗する事例にも意外とヒントがありますですが失敗事例は中々ネット上には落ちていませんので事業展開を考えた時に… ・何をしたいのかのコンテンツを探る・事業展開の人材選定をする・具体的な戦略会議をして実施可能か検討する など、展開したい事業含めて経営計画を策定したとしても、実際に実行していくのは社員になります。人が惚れるような事業展開を考えマネジメントできてこそ成功に近づくでしょう。 |
事業展開を実行するときの考え方

ここからは、実際に事業展開を実行するときに持つべき考え方について説明します。
- M&Aをして他事業の展開をする
- 自社事業のノウハウを活かした事業を展開する
- 海外進出に関連するかどうかで展開をする
- 主軸事業が落ち込んでいる時に補える事業なのかを判断する
以下で詳しく見ていきます。
M&Aをして他事業の展開をする
M&Aとは、企業・事業の合併や買収の総称を指します。
M&Aによって他社を買収した場合、必然的に同社が営んでいた新たな事業を手掛けることになるわけですが、あらかじめ自社の既存事業とうまく統合を図ることができれば、より速やかに効果を発揮できる期待が持てるでしょう。
したがって、M&Aの中長期的な成功が事業展開を行う意味につながります。
自社事業のノウハウを活かした事業を展開する
新規事業のアイデアを生み出す方法を大きく分けると、既存事業の技術やリソース・ノウハウを活用する方法と、全く新しい事業に取り組むという2つのパターンがあります。
和菓子の「いちご大福」のように、一見、独創的で革新的に見えるサービスでも、元は既存のリソースの組み合わせで成り立っていることが大半です。
既存の技術やリソース・ノウハウの価値を再評価するとアイデアのイメージが広がります。
事業立ち上げの負担やリスクが低いことも、既存の自社のノウハウで新規事業を始めるメリットとして挙げられます。
海外進出に関連するかどうかで展開をする
海外進出を図りたいというのも、事業展開の目的の一つとしてよくあるケースです。
国内では成長に陰りが見えているものの、海外に目を向ければまだまだ飛躍の余地が大いに残されている事業は少なくありません。
ただし、国内で評価されている商品やサービスが、そのまま海外でも受け入れられるとは限りません。
進出先のマーケットをしっかりと調査し、その国に合うように自社の商品やサービスをローカライズするところまで視野に入れましょう。
主軸事業が落ち込んでいる時に補える事業なのかを判断する
マーケットの投資で重要なのは、分散だとよく言われます。
経営も広い意味では投資ですから、同じようにリスクの分散が重要です。
主軸になる事業が落ち込んでいる時に、その落ち込みを補える事業なのかを判断したうえで事業展開していくと、不況に強い事業グループが形成できます。
監修コメント
| 良くも悪くもリスクはあります。ある事例で言うと違う分野に進出したいがためにM&Aをしました。しかし、全く自社のサービスとは違う分野だったのでM&Aされた社員の心を掴めず崩壊したと言う事例もあります。様々なリスクがある中、経営判断をしなければなりません。例え新業態のビジネスのM&Aだとしても経営理念・事業計画をしっかり作成しM&Aの社員が惚れるようにコミニュケーション形成していくと良いと思います。 |
事業展開後に必要なこと
ここからは、事業展開を進めていった後に必要なことについて3つのポイントを紹介します。
- 認知拡大
- 顧客育成
- サービスの信頼性工場
以下で詳しく見ていきます。
認知拡大
まずは、認知拡大です。
一部のケース、たとえば既存の企業をM&Aで買収した場合や事業展開がニュースになったときを除けば、新規事業の認知度は低いのが通常です。
そこで、広告を戦略的に打つなど、認知拡大は必要不可欠といえます。
顧客育成
顧客の育成とは少し耳慣れない言葉かもしれませんが、顧客のロイヤルティ、つまり自社への好感などを育成していくという意味です。
ロイヤルティの高い顧客は、購買促進のための広告活動だけでなく、好意・好感を高めてもらうためのブランディングが必要です。
サービスの信頼性向上
新しいサービスは、実績の積み上げがまだ少ないので、信頼性の向上が必要です。
特にITやシステム関係のサービスについては、信頼性への注目が高まっているので、安定してサービスを提供し続けられるかどうかは重要です。
監修コメント
| 絶大な信頼で契約したクライアントに対して、自社のサービスで成功したとします。そのクライアントに対して、今後の未来が見えるようなサービスを展開出来るように、自社のサービスを充実させ、徐々にビジネスが大きくなるようなことも考えていくのも必要です。 |
事業展開は段取りが重要!主軸事業との親和性も考えよう
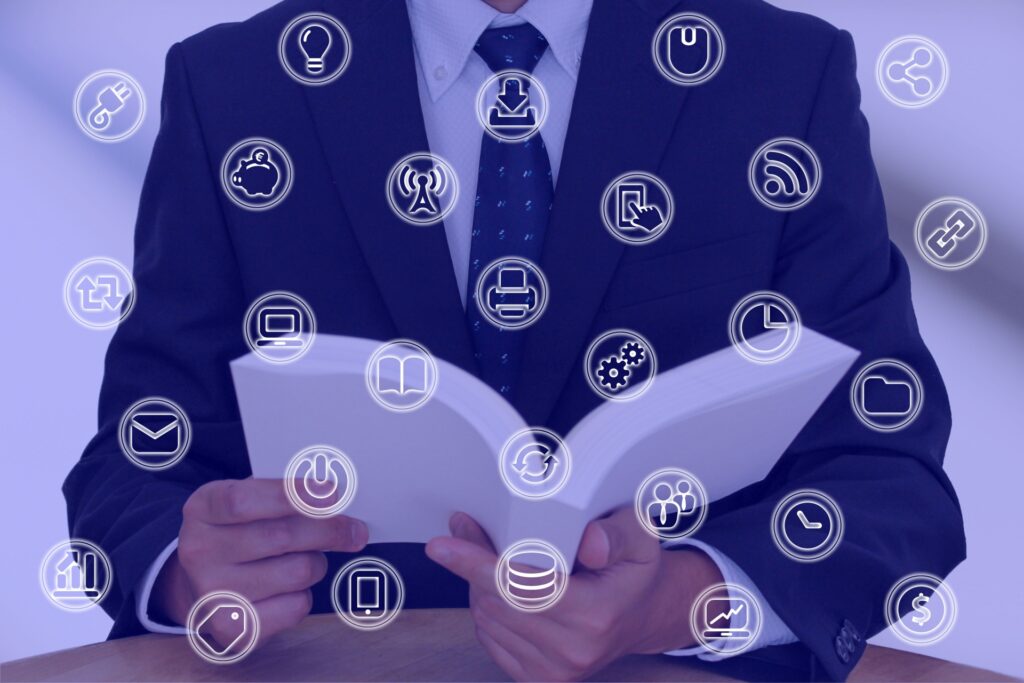
本記事では、事業展開の考え方や戦略、経営計画の作成方法を解説してきました。
- 案出し、人材選定、実現可能性の検討、経営計画の修正、市場調査といったステップを確実に実行する必要あり
- M&Aをするか、自社事業のノウハウを活かすかなどの観点を持つ
- 事業展開後にも認知拡大・顧客育成・信頼性向上を継続的に行う
事業展開というとクリエイティブな側面が強いように思われますが、中身は地道な調査・検討の積み上げが大半です。
このような段取りを確実に行っていくことが重要です。
行き詰まったときや、よりスムーズな事業展開を行いたいときは、経営コンサルタントに相談するのもひとつの手でしょう。