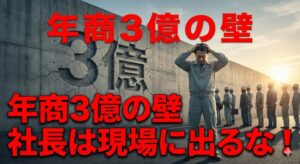建設業の利益構造を根本から強くする経営デザイン戦略
2025年11月22日
「現場は回り続けている。売上も少しずつ伸びている。しかし、なぜか利益率が下がり続け、資金繰りが楽にならない」
年商5億円〜9億円規模の建設会社社長にとって、これは最も深刻で、かつ共通の悩みです。
結論を申し上げます。貴社の利益が増えないのは、現場の努力不足ではありません。ビジネスの「設計図(経営デザイン)」自体が、利益が出にくい構造になっているからです。
本記事では、外資系コンサルティングファームが用いる構造改革の手法を建設業向けにアレンジし、根本的な利益体質へ転換するための「3つのデザイン戦略」を解説します。
1. なぜ「頑張れば頑張るほど」利益が減るのか?
建設業、特に下請け構造の中にある企業は、何も手を打たなければ「貧乏暇なし」のスパイラルに陥る力学が働いています。
年商10億手前で成長が止まる企業の共通点
- 変動費の高騰:資材・労務費が上がり、従来の粗利率を維持できなくなっている。
- 固定費の肥大化:管理部門や営業人員を増やしたが、それに見合う利益を生んでいない。
- 価格決定権の欠如:元請けの言い値で受注し、「断ると次がない」という恐怖に支配されている。
この状態から抜け出すには、現場の改善(Operation)だけでは不可能です。経営の構造(Design)を書き換える必要があります。
2. 解決策:3つの「経営デザイン」を再構築せよ
高収益企業への転換に必要なのは、以下の3つの要素を意図的にデザインし直すことです。
① 案件デザイン(Unit Economics)
「売上」ではなく「粗利総額」をKPIにします。赤字現場は、会社の血液(キャッシュ)を流出させる傷口です。
施策:過去の現場を分析し、粗利率20%以下の顧客とは、値上げ交渉が決裂した時点で取引を停止する勇気を持ってください。「売上が下がる」恐怖よりも、「利益が残る」安心感を手に入れるためです。
② 組織デザイン(Standardization)
社長が全ての見積もりと工程管理を行っている限り、年商5億〜7億が限界値です。
施策:見積もり基準の標準化(ツール化)と、現場権限の移譲を進めます。「社長がいなくても回る現場」を一つずつ増やすことが、スケーラビリティ(拡張性)を生みます。
③ 財務デザイン(Balance Sheet Strategy)
利益が出ても、税金対策で無駄な経費を使ってはいけません。税金を払い、内部留保(自己資本)を厚くすることが、銀行格付けを上げ、次の大型案件を受注するための信用力になります。
3. 実践ロードマップ:構造改革のステップ
明日から着手できる具体的なアクションプランです。
- Phase 1(1〜2ヶ月目):全取引先の粗利率を可視化し、「切るべき案件」を特定する。
- Phase 2(3〜5ヶ月目):浮いたリソースを使い、原価管理ソフトの導入と社内ルールの統一を行う。
- Phase 3(6ヶ月目〜):強固になった財務基盤を背景に、より条件の良い新規元請けや直需案件への営業を開始する。
まとめ:経営者が描く「設計図」が会社の未来を決める
建設業の利益構造は、自然には良くなりません。経営者が強い意志を持って「利益が出るようにデザイン」する必要があります。
現場の忙しさに逃げず、まずはデスクに座り、自社の利益構造(設計図)を見直すことから始めてください。
貴社の「利益構造」に欠陥はありませんか?
当社では、建設業経営者に特化した経営構造改革コンサルティングを行っています。
現状の決算書と取引状況を分析し、どこに利益漏れがあるかを特定する
60分間の無料オンライン戦略相談をご利用ください。
※ 営業代行の売り込み等は一切いたしません。
※ 毎月5社限定での受付となります。