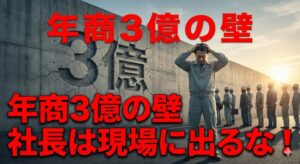黒字を継続させる外資系コンサル式・経営構造の作り方
2025年11月22日
「売上は順調に伸びて5億円を超えた。しかし、なぜか手元資金はかつてないほど逼迫している」
これは、年商3〜10億円規模を目指す建設会社経営者から最も頻繁に寄せられる相談です。
結論から申し上げます。あなたの会社が利益を残せないのは、営業努力が足りないからでも、職人の腕が悪いからでもありません。ビジネスモデルそのものに、利益が漏れ出す「構造的な欠陥」があるからです。
本稿では、外資系コンサルティングファームが企業の再生局面で使用するフレームワークを建設業向けに最適化し、「黒字を継続させる経営構造」の具体的な構築手法を解説します。
1. なぜ「売上拡大」が「利益縮小」を招くのか?
多くの経営者は「売上さえ上がれば、利益は後からついてくる」と考えがちです。しかし、下請け構造が中心の建設業において、無計画な拡大は致命傷になります。
我々が分析する限り、年商5億の壁で停滞する企業は、例外なく以下の「貧困化サイクル」に陥っています。
図1:労働集約型から「構造的黒字」への転換イメージ
このサイクルを断ち切るには、「頑張って働く」ことではなく、「利益が出る構造」を設計(Design)することが必要です。
2. 黒字を継続させる「3つの経営構造」改革
外資系コンサルティングにおいて、企業の再成長プランを描く際は必ず以下の3つの要素(Strategy, Operation, Finance)を連動させます。建設業に置き換えると、以下のようになります。
① ポートフォリオ構造の改革(元請開拓・撤退戦)
全ての顧客が「神様」ではありません。データを分析すれば、利益をもたらす顧客と、リソースを奪うだけの顧客は明確に分かれます。
- 施策:過去3年分の工事台帳を分析し、顧客ごとの粗利率を算出する。
- 構造化:粗利20%未満の元請けとは「値上げ交渉」か「取引停止」を行う。空いたリソースで、高単価が見込める新規元請けや直需案件(元請開拓)へシフトする。
② オペレーション構造の改革(DX・脱属人化)
「社長しか見積もりができない」「現場の状況は電話しないと分からない」。この状態が成長のボトルネックです。DX(デジタルトランスフォーメーション)の本質は、ツールの導入ではなく「判断基準の標準化」にあります。
- 施策:原価管理ソフトを導入し、実行予算と発注金額の差異をリアルタイムで可視化する。
- 構造化:社長の承認プロセスを「例外事項」のみに限定し、日常業務は社員だけで完結するフローを構築する。
③ 財務構造の改革(銀行格付け・資金調達)
黒字倒産を防ぎ、大規模な投資(採用・機材・M&A)を行うには、「銀行格付け」を意識した決算書作りが不可欠です。
- 施策:役員借入金の資本組み入れや、減価償却の適正化を行い、自己資本比率を改善する。
- 構造化:金融機関が評価する指標(債務償還年数など)をKPIに設定し、融資を受けやすい(=キャッシュが尽きない)体質を作る。
図2:経営構造を支える3つの階層
3. 実践ロードマップ:明日から着手すべきこと
概念は理解できても、実行できなければ意味がありません。以下のステップで「改善」を進めてください。
- 現状分析(Week 1):直近1年の全現場の粗利率を洗い出し、赤字・低収益の原因(見積もりミス?現場トラブル?顧客の単価?)を特定する。
- 止血処置(Week 2-4):利益を食いつぶしている「悪い赤字工事」や「採算割れの取引先」に対し、条件変更または撤退の意思決定を行う。
- 構造構築(Month 2-6):原価管理システムの導入と、営業ターゲットの再設定(高単価な元請けへのアプローチ)を並行して進める。
図3:ステップ・バイ・ステップでの改善フロー
結論:社長の仕事は「現場」ではなく「経営」である
黒字を継続させる構造を作るためには、社長自身が現場のプレイヤーから抜け出し、数値に基づいた経営判断を行う「真の経営者」へと変貌する必要があります。
「忙しくて改革の時間がない」とお考えかもしれません。しかし、今の構造のまま走り続けても、行き着く先は疲弊です。今こそ、外資系コンサルタントの視点を取り入れ、経営構造の抜本的な改革に着手すべき時です。
貴社の「利益構造」を診断しませんか?
当社では、年商1〜10億円規模の建設業経営者に特化した
経営戦略コンサルティングを提供しています。
「今の粗利率は適正か?」「銀行格付けを上げるには?」
まずは現状の課題を整理する60分間の無料オンライン戦略相談をご利用ください。
※ 営業代行や人材紹介の売り込み等は一切いたしません。
※ 毎月5社限定での受付となります。