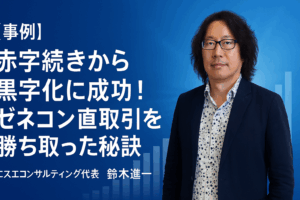建設業が黒字倒産を防ぐキャッシュフロー改善の実践方法
2025年9月30日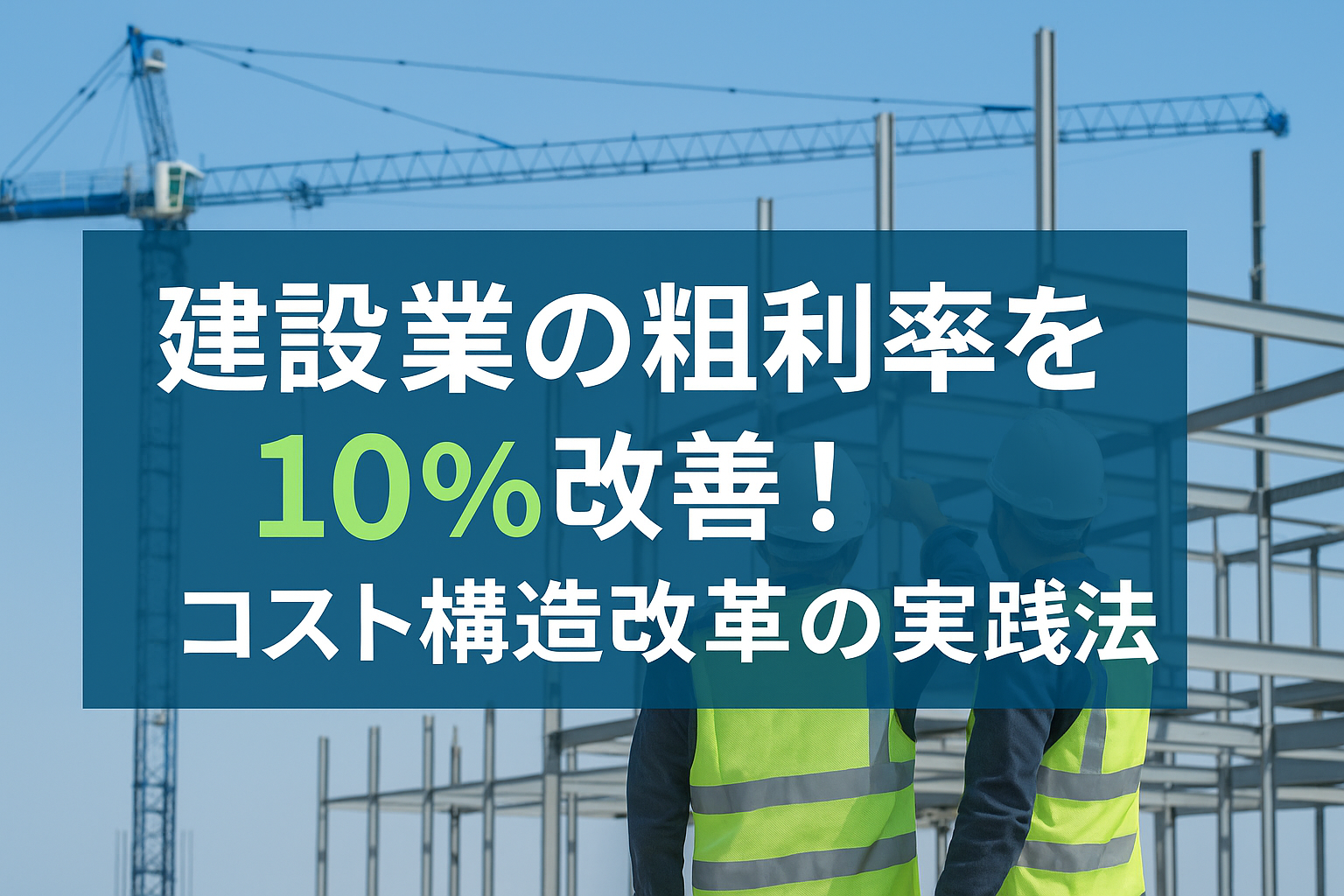
建設業のコスト構造改革|粗利率を10%改善する原価管理
建設業において利益を左右するのは「売上」よりも「原価管理」です。
本記事では、粗利率を10%改善した企業事例を交えながら、固定費・変動費のコントロール・KPI設計・現場ごとの損益管理を実現する方法を解説します。
建設業の原価構造の基本
建設業は「売上高-原価=粗利」で利益構造が決まります。原価率が1%変動するだけで利益が数百万円単位で動く業界です。
- 直接原価:材料費・外注費・労務費
- 間接原価:現場管理費・安全管理費・共通仮設費
- 固定費:本社人件費・家賃・減価償却費
粗利率改善の第一歩は「原価の見える化」です。
粗利率を下げる典型的な要因
- 見積段階での原価積算ミス
- 追加工事・仕様変更の未請求
- 現場ごとの原価管理が遅れる(月次集計のみ)
- 固定費が売上規模に比して高止まり
粗利率を改善する原価管理の仕組み
1) 固定費と変動費の見える化
費用を「売上連動(変動費)」と「売上非連動(固定費)」に分類し、毎月の固定費比率を把握します。
2) KPIによるプロジェクト管理
プロジェクトごとに以下をKPI化します:
- 粗利率(目標値:20%以上)
- 出来高と原価進捗の差異
- 追加工事・変更の請求率
3) 現場ごとの損益管理
工事ごとに損益計算を行い、粗利率をリアルタイムで監視します。赤字案件を早期に把握する仕組みが重要です。
粗利率10%改善の企業事例
事例①:中堅ゼネコン
- 課題:粗利率15%→原価高騰で10%まで低下
- 施策:現場別損益管理表の導入/追加工事請求の徹底
- 結果:1年で粗利率20%へ回復、年間利益+3,000万円改善
事例②:工務店(売上6億円)
- 課題:営業案件は多いが、原価管理が属人的
- 施策:KPIによる現場管理+固定費削減
- 結果:粗利率22%→32%に改善、借入依存度を低下
今日から始められる改善チェックリスト
- □ 原価を「直接費・間接費・固定費」に分けて管理しているか
- □ 現場ごとの粗利率を週次で把握できているか
- □ 追加工事・仕様変更はすべて請求に反映しているか
- □ 固定費比率を毎月算出し、改善計画を立てているか
無料相談のご案内
あなたの会社もコスト構造を改革し、粗利率を改善しませんか?
具体的な改善策を、御社の実情に合わせてご提案します。