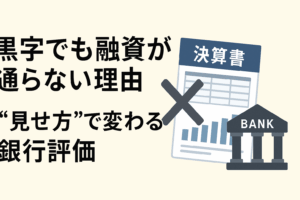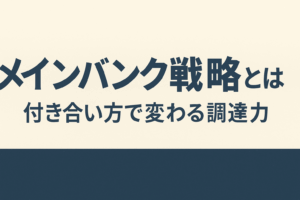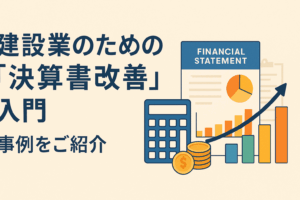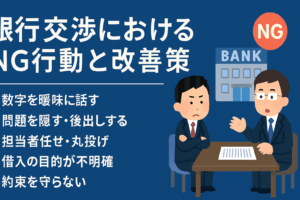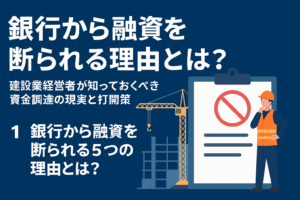建設業の決算書で見られるポイント|金融機関の評価軸を徹底解説 3
2025年8月2日
建設業の決算書で見られるポイント|金融機関の評価軸を解説
はじめまして。エスエスコンサルティング株式会社の鈴木進一です。
私はこれまで30年以上、建設業の経営支援に携わり、財務改善や資金調達、事業再生の現場に立ち会ってきました。
この記事では、金融機関が建設業の決算書をどう読み、どこを評価しているのか、実践的な視点でわかりやすく解説します。
目次
- 建設業の決算書とは?
- 金融機関が注目する「3つの視点」
- 評価される主要指標とその意味
- 赤字でも評価される会社の特徴
- 銀行が嫌う決算書の共通点
- 決算書改善の実践ポイント
- 金融機関に響く「補足資料」とは
- ケーススタディ:評価アップ事例
- 中小建設業者が今すぐできる改善策
- まとめ|決算書は「未来の約束状」
1. 建設業の決算書とは?
建設業の決算書は、単なる過去の成績表ではありません。
売上、利益、資産、負債などの数字を通じて、「この会社が将来も安定して事業を続けられるか」を示す「信頼の証明書」です。
- 受注産業特有の売上認識(完成工事高・未成工事支出金)
- 材料費・外注費・労務費の変動が大きい原価構造
- 入金と支払のタイミングにギャップがある資金繰り
2. 金融機関が注目する「3つの視点」
- 収益性: ちゃんと稼げているか?利益が出ているか?
- 安全性(財務健全性): 借金過多ではないか?資産と負債のバランスは良いか?
- 成長性・持続性: 今後も成長・継続できそうか?一過性の数字ではないか?
3. 評価される主要指標とその意味
- 完成工事総利益率(粗利率)…15%以上あれば優良、10%を切ると警戒。
- 営業利益率…3%程度で優秀、赤字は厳しく評価。
- 自己資本比率…20%未満は要注意、ゼロやマイナスは融資困難。
- 流動比率…120%以上が理想、100%未満は資金繰りリスク。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ…3倍以上が目安、利息支払い難は警戒対象。
- 未成工事支出金・完成工事未収入金の管理状況。
4. 赤字でも評価される会社の特徴
- 赤字の理由が明確(設備投資、人材採用など未来志向)
- 受注残が多く、翌期黒字化の見込み
- 一時的な特別損失が影響した場合
5. 銀行が嫌う決算書の共通点
- 粉飾決算(売上前倒し、原価圧縮)
- 役員貸付金・仮払金が多い
- 不明瞭な未成工事項目
- 売上急減・急増の説明不足
6. 決算書改善の実践ポイント
- 粗利率の見直し
- 不要資産・負債の整理
- 役員貸付金の清算
- 未成工事の見える化
- 入金・支払いサイト短縮
- 中期経営計画策定・共有
7. 金融機関に響く「補足資料」とは
- 受注残高一覧
- キャッシュフロー計画
- 原価・現場別採算表
- 3カ年計画
- 組織・管理体制資料
8. ケーススタディ:評価アップ事例
A社(年商7億円・足場工事業)は、粗利率12%、自己資本比率5%、役員貸付金2億円の状況でした。
- 原価管理改善で粗利率16%
- 役員貸付金半減
- 中期計画策定・銀行提出
結果、運転資金枠が2倍(3000万→6000万)に。
9. 中小建設業者が今すぐできる改善策
- 現場別粗利の見える化
- 請求・回収体制の整備
- 役員貸付金・仮払金整理
- 金融機関と定期対話
10. まとめ|決算書は「未来の約束状」
決算書は「過去の結果」でなく「未来の約束状」。金融機関はそこから、返済能力と成長可能性を読み取ります。
着実な改善と説明責任が、信頼構築の第一歩です。
【無料相談受付中】
エスエスコンサルティング株式会社では、建設業の決算書分析・改善アドバイスを行っています。
資金繰りや金融機関対策でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。