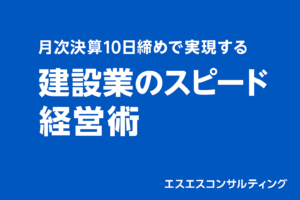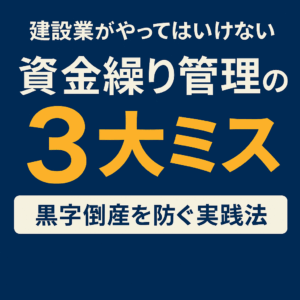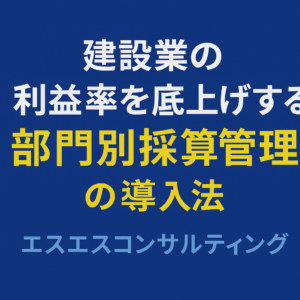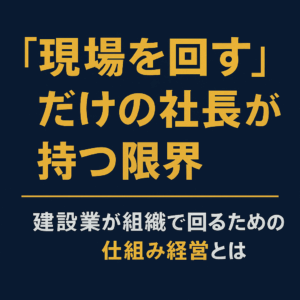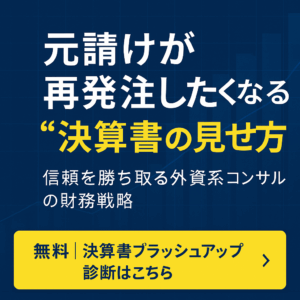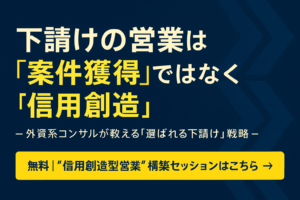黒字倒産を防ぐ!建設業が今すぐ導入すべき管理会計とは?第1回
2025年9月24日
建設業で黒字倒産が増えています。帳簿上は利益が出ているのに、資金繰りが回らず会社が立ち行かなくなる――。その原因の一つが、財務会計だけに頼った経営管理です。
本記事では、黒字倒産の実態と原因を整理し、管理会計を導入することで得られる効果や実践方法を、事例とともに解説します。
黒字倒産とは?建設業に潜むリスク
「黒字倒産」とは、決算上は利益が出ているにもかかわらず、手元資金が不足して倒産に至る現象を指します。
特に建設業は、工事の受注から売上計上までに長い時間がかかり、外注費・材料費の支払いが先行する業種です。そのため、以下のような要因で資金ショートに陥りやすいのです。
- 入金と支払いのタイムラグ(入金120日、支払い30日など)
- 現場ごとに利益率が大きく異なる
- 赤字工事を受注してしまっても気づきにくい
- 原価が後から確定するため、工事中は損益が見えにくい
このような特性から、建設業では「決算上は黒字=安心」とは言えないのです。
財務会計だけでは会社を守れない
多くの経営者が「決算書を見れば会社の状況がわかる」と考えています。しかし財務会計は、税務申告や外部への報告を目的とした「過去の数字の整理」であり、経営判断に必要な情報をリアルタイムで提供してくれるわけではありません。
一方で、経営者が意思決定に活用できる数字を提供するのが「管理会計」です。管理会計は未来を見据えた数字の活用であり、部門別・現場別の損益や資金繰り予測を行うことが可能です。
管理会計導入で得られる3つの効果
① 工事ごとの損益が見える
管理会計を導入すれば、案件単位での粗利率や採算を把握できます。赤字が出ている現場を早期に察知し、経営資源を集中させる判断が可能になります。
② キャッシュフローが予測できる
入金・支払いのタイミングを管理会計に取り込むことで、将来の資金繰りをシミュレーションできます。これにより、資金ショートの危険を事前に防ぐことができます。
③ 経営会議の質が向上する
損益やキャッシュの見える化は、経営会議の議論を「感覚」から「数字」に変えます。これにより、経営陣の意思決定が早くなり、現場への指示も明確になります。
導入事例:粗利率を7%から12%に改善したA社
A社は中堅規模の建設会社で、毎年黒字を計上していたものの、資金繰りに常に不安を抱えていました。
管理会計を導入したことで、現場ごとの損益が可視化され、赤字工事を排除することができました。
また、採算性の高い案件に人員と資材を集中させる戦略を取った結果、粗利率は7%から12%に改善。さらに銀行からの評価も高まり、安定的な資金調達が可能になりました。
数値で見る管理会計の効果
仮に粗利率が7%から10%に改善した場合、年商10億円の会社では、営業利益は3,000万円増加します。
この増加分は、資材の先行投資や人材育成に回すことができ、企業の成長力を高める好循環を生み出します。
管理会計導入の5ステップ
- 現状把握:既存の財務データと現場データを整理する
- 原価計算の整備:直接工事費・間接費を分け、工事ごとに集計する
- 部門別損益の作成:現場単位・部門単位で利益を可視化する
- キャッシュフロー予測:入出金のタイミングを織り込んで将来資金をシミュレーション
- 定着化:月次の経営会議に取り入れ、習慣化する
エスエスコンサルティングの強み
当社は建設業を中心に、現場の実態に即した管理会計導入支援を行っています。単なるシステム導入ではなく、経営者・幹部・現場監督が「数字を経営に活かす力」を身につけられるよう伴走型で支援します。
特に「粗利率改善」「黒字倒産防止」「銀行格付け対策」に直結する指導が評価されています。
無料相談のご案内
「うちの会社も黒字倒産のリスクがあるのでは?」と感じたら、まずはお気軽にご相談ください。
エスエスコンサルティング株式会社では、無料の経営診断を通じて御社の課題を分析し、管理会計導入による改善シナリオをご提案いたします。
まとめ:管理会計は黒字倒産を防ぐ最強の武器
財務会計は過去を整理するもの、管理会計は未来を描くもの。
建設業こそ管理会計を導入し、工事ごとの利益とキャッシュフローを見える化する必要があります。
黒字倒産を防ぎ、持続的成長を実現するために、今すぐ管理会計の導入を検討しましょう。