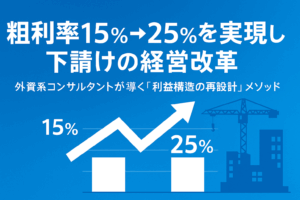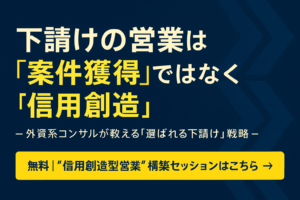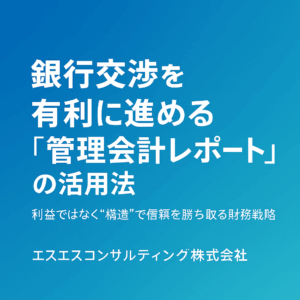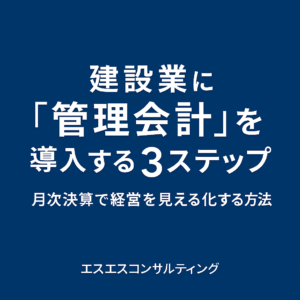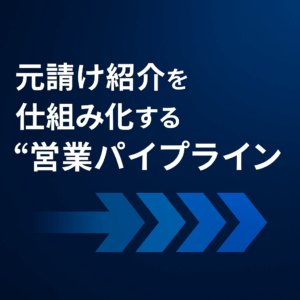銀行格付けを1ランク上げる「月次報告書」の作り方
2025年11月19日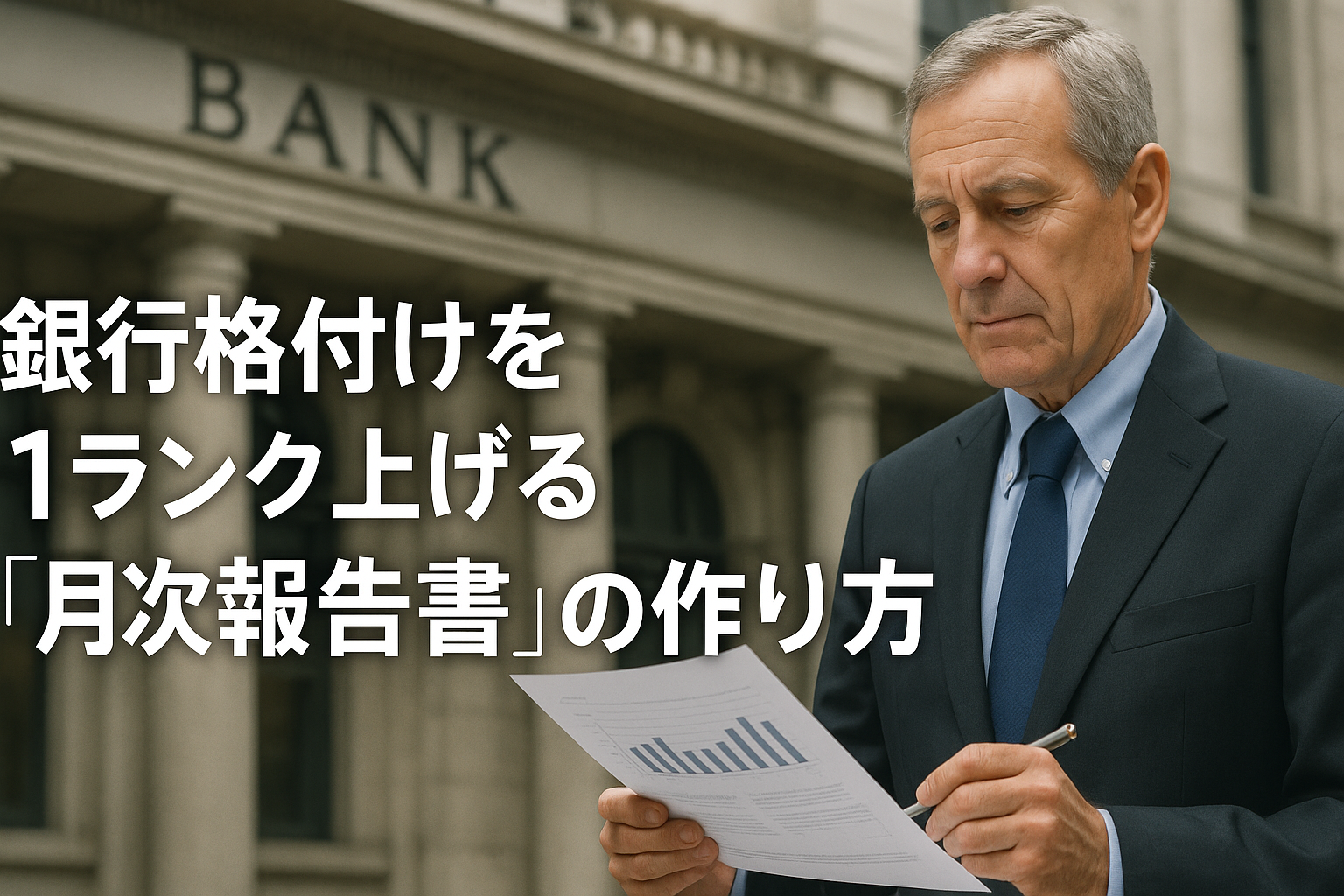
銀行格付けを1ランク上げる「月次報告書」の作り方
銀行格付けを上げるために最も効果があるのは、 決算書ではなく「月次報告書」です。
理由は明確で、銀行が本当に見たいのは、 「この会社は毎月どのように経営しているのか?」 という“経営の習慣”だからです。
決算書は「結果」ですが、 月次報告書は「思考とプロセス」を示します。
外資系コンサルの視点で、 銀行が格付けを必ず上げる報告書の作り方を公開します。
■ なぜ月次報告書が“格付けを左右する”のか?
銀行は企業の「姿勢」と「習慣」を非常に重視しています。
- 毎月数字を締めている → 経営管理ができている
- 改善を繰り返している → 将来キャッシュが安定する
- 説明資料が整っている → 事故を起こさない企業
つまり月次報告書は、銀行に対しての “経営者としての信用残高”を積み上げる行為そのもの。
銀行格付けは、数字より「経営の透明性」で決まります。
■ 銀行が評価する月次報告書:必須の7要素
以下の7つを入れるだけで、 銀行の評価がガラッと変わります。
① 月次PL(前年比・予算比)
銀行が最も見る数字は「粗利」と「営業利益」。 前年比・予算比を並べて“意図的な経営”を示す。
② キャッシュフローの動き
- 入金予定
- 支払予定
- 運転資金の増減
銀行は赤字よりも“資金ショート”を嫌う。
③ 粗利率の推移(3ヶ月・6ヶ月)
短期で改善しているかどうかで、 銀行は経営力を判断しています。
④ 案件別の採算表(建設業は必須)
- 見積粗利率
- 実行粗利率
- 差異の理由
この1枚があるだけで、銀行の目の色が変わる。
⑤ 財務KPI(格付けに直結)
最低限、以下を毎月提出:
- 自己資本比率
- 借入金月商倍率
- 営業利益率
- EBITDA
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
⑥ 経営課題と改善アクション
経営者の“考えている量”が伝わる部分。
銀行の評価ポイントは、 問題があるかどうかではなく 問題をどう扱っているかです。
⑦ 来月の見通しとリスク対策
未来視点のある会社を銀行は高く評価する。
■ 格付けを上げる月次報告書の“構造テンプレート”
以下の構造をそのまま使うと、 銀行は文句のつけようがありません。
① 月次PL(前年比・予算比) ② キャッシュフロー(今月→翌月) ③ 粗利率の推移(3–6ヶ月) ④ 案件別採算表 ⑤ 財務KPIの推移 ⑥ 今月の課題と対策 ⑦ 来月の見通し ⑧ 経営者コメント(1分で読める量)
銀行が欲しい情報を“順番通りに”並べることがポイント。
■ 銀行格付けが1ランク上がると何が起きるのか?
- 調達金利が下がる
- プロパー融資が通りやすくなる
- 融資枠が広がる
- 信用保証協会の付け替えが通る
- 借換えがしやすくなる
つまり、 月次報告書は「資金調達コスト」を下げる武器になります。
■ 銀行は“完璧な会社”を求めていない
銀行は決して、完璧を求めていません。
求めているのは、ただ1つ。
「この会社は、毎月経営を改善しているか?」
月次報告書は、その証明書です。
きちんと作るだけで、格付けは必ず上がります。
銀行格付けを上げる“財務の仕組み”を導入したい経営者へ
・格付け6の壁を越えたい
・プロパー融資を取りにいきたい
・月次管理が弱い
・銀行との関係性を強くしたい
外資系コンサルティングのフレームで、
『格付けを上げる月次報告書』を御社専用に設計します。