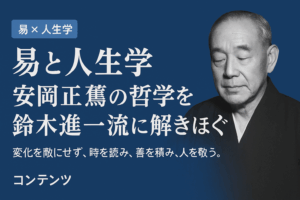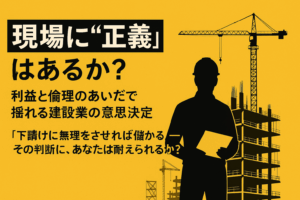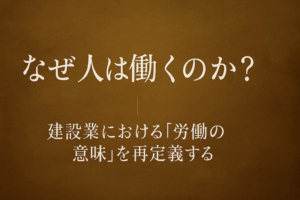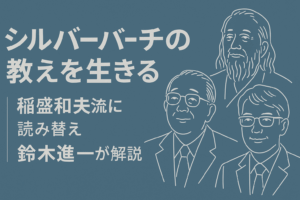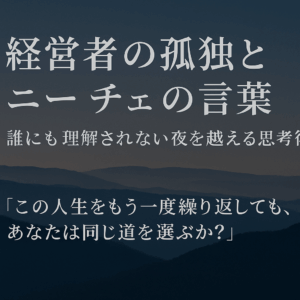評価されない仕事をする意味|ハイデガーと共に考える現場と存在
2025年7月25日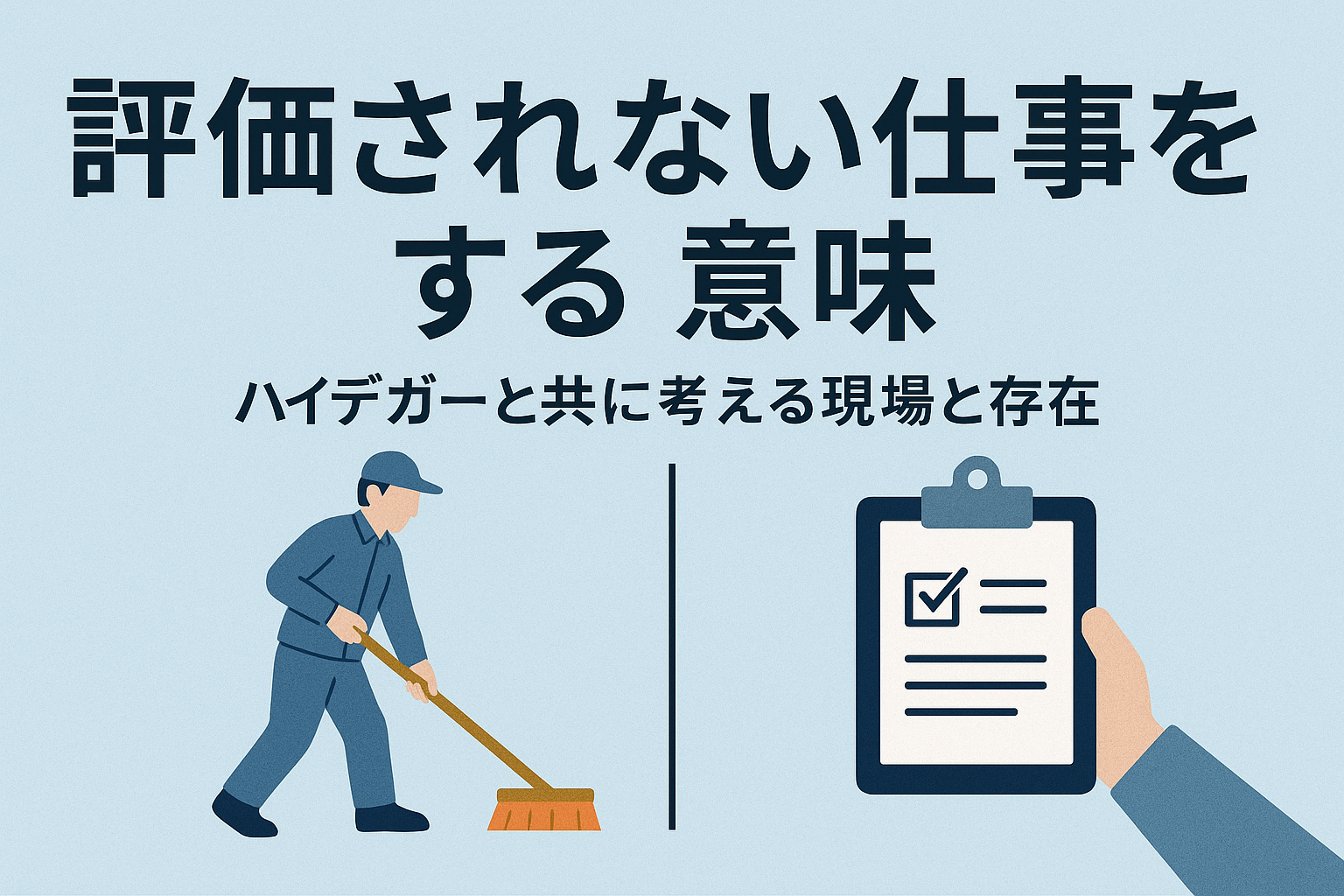
評価されない仕事をする意味|ハイデガーと共に考える現場と存在
― 存在が語られずに、評価だけが独り歩きする世界で ―
1. 評価されない仕事に意味はあるのか?
建設現場、清掃業、介護、配送。
社会インフラを支えるこれらの仕事は、時に「誰かに褒められることもなく」淡々とこなされる。
報酬も高くなく、注目も集めない。それでも、誰かがやらなければ社会が止まる。
なぜ、私たちは「評価されない仕事」に向き合えるのか?
そこに“意味”はあるのか?
哲学者ハイデガーの思想は、現場で働くすべての人へのヒントを与えてくれる。
2. ハイデガーとは誰か?
マルティン・ハイデガー(Martin Heidegger)は、20世紀ドイツの哲学者で「存在とは何か?」を生涯問い続けた存在論の大家。
彼の主著『存在と時間』では、私たち人間が「世界のなかにある」という根源的な立ち位置を、「現存在(ダーザイン)」という独自の言葉で捉えた。
ハイデガーの視点では、仕事も人生も「意味があるかどうか」ではなく、「本来的に生きているかどうか」が問われる。
3. 「現場」とは、存在が“開かれて”いる場所
ハイデガーの思想のなかで、「道具性」の概念がある。
たとえば、ハンマーは「釘を打つため」に存在する。その意味は、使用される“現場”において初めて立ち上がる。
同じく、建設業の道具も、介護の言葉も、配送のハンドルも、それが“使われる場”でこそ「意味」が現れる。
つまり、現場とは「存在が意味を持つ空間」であり、人間が世界に“投げ出されている”ことを実感できる場所でもある。
4. 「評価」とは、世界に回収される作業
一方で「評価」は、ハイデガー的には“没落”を意味する可能性もある。
なぜなら、評価とは「他者の視点」であり、「本来的な存在」ではなく「世間的な存在」を優先させるからだ。
SNSの「いいね」、上司からの表彰、給与の多寡。
それらは生きる指針になり得るが、本来の「自分の在り方」を見失わせる危険も孕む。
5. なぜ“誰にも見られていない労働”が尊いのか?
誰にも気づかれず、誰にも称賛されずとも、今日も誰かがマンホールの下で作業をしている。
深夜に道路工事をし、ゴミを回収し、高所で作業をしている。
それは「評価される」ためではなく、「世界を支える」ため。
ハイデガーがいう「本来的な存在」とは、まさにこのような、“世界と直接つながっている仕事”のなかにある。
6. 自分の存在を、世間に委ねるな
ハイデガーは、私たちが陥りやすい「世人(ダス・マン)の支配」を警告した。
「みんながそうしてるから」「普通はこうだから」という思考停止は、自分を“誰でもない誰か”に変えてしまう。
評価されない仕事にこそ、逆説的に“自由”がある。
誰にも支配されず、ただ目の前の世界と向き合う時間。それは、「現存在」であることを最も実感できる時間かもしれない。
7. 最後に:評価よりも、存在を選べ
ハイデガーは「死を前にしたときに、人は本来的になる」と言った。
他者の評価も、SNSのフォロワー数も、最期には意味をなさない。
だからこそ、いまこの瞬間、自分が何をしているか。
評価されなくても、そこに“意味”を与えられるかどうか。
建設業、介護、清掃、物流…
評価されにくい仕事こそ、世界と深くつながっている。
そこには、誰よりも“人間らしい存在”がある。
――今日も「現場」で汗をかくあなたへ。
存在の尊厳は、評価の有無に左右されない。
次の一歩は、経営者としての“問い”を持つことから。
「我が社は、いまどう進化させるべきか?」
その問いに、私たちは共に向き合います。
30分の無料戦略相談で、現状の可視化と次のアクションを見つけてください。