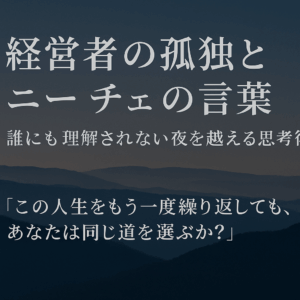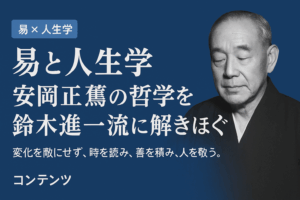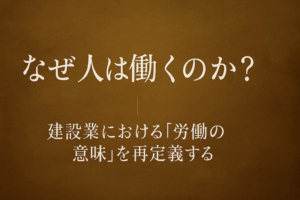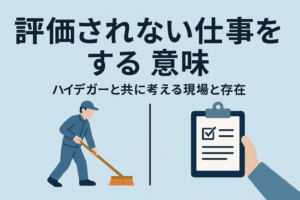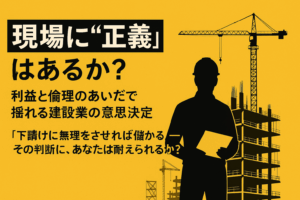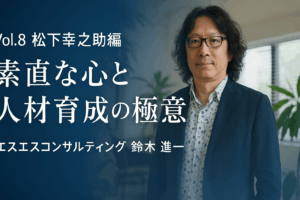正解のない経営にどう向き合うか|ソクラテスに学ぶ“問う力”
2025年7月26日
エスエスコンサルティング株式会社の鈴木進一です。
経営の世界には、「正解」がありません。
過去の成功モデルが明日も通用するとは限らず、完璧なマニュアルも存在しません。
それでも、意思決定をしなければならない――。それが、経営者という立場です。
そんな“不確実な世界”において、今こそ必要なのは「問う力」。
自分に、社員に、顧客に、社会に――問い続けることでしか、見えてこない“本質”があります。
本記事では、古代ギリシアの哲学者ソクラテスの問いの技術、いわゆる**ソクラテス式問答法(ソクラティック・メソッド)**を手がかりに、
現代の経営に通じる「正解なき時代の思考術」について考察します。
⸻
第1章|正解のない時代に、経営者はどう立つべきか?
“VUCA”という言葉がビジネスの世界でも浸透して久しい。
Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)。
経営環境は年々不安定になり、1年前の常識が今では通用しない。
そんな時代に、経営者は何を拠り所に意思決定をすれば良いのでしょうか?
まず大切なのは、「正解を探す」という発想を捨てることです。
経営においては“答えのない問い”と向き合い続ける覚悟が必要です。
正解は、他者に求めるものではなく、自ら問うものへとシフトしていく必要があります。
⸻
第2章|ソクラテスが実践した「問う力」の哲学
ソクラテスは「自分が無知であることを知っている者が、最も賢い」と説きました。
彼の生き方は、権威や慣習に従うのではなく、対話を通して真理を探究するものでした。
“ソクラテス式問答法”は、あらかじめ答えを与えず、質問によって相手に考えさせ、自らの矛盾に気づかせる方法です。
これは、単なるテクニックではなく、「他者とともに問いを深める文化」をつくるための思考様式でもあります。
経営においても、従業員の思考力を引き出す“問いのデザイン”が、組織の創造性を高めます。
⸻
第3章|組織に“問う文化”をつくる
現場で「質問しにくい」「疑問を言うと嫌がられる」という空気がある会社は、思考停止に陥ります。
経営者が全てを答えてしまう文化では、部下は考えなくなり、成長の芽が摘まれてしまうのです。
問う文化をつくるには、次のような工夫が有効です:
•会議で「問い」を議題にする(例:「この施策の前提は正しいか?」)
•沈黙を許容する(すぐに答えが出ないことを前提に)
•役職に関係なく問いを歓迎する風土づくり
問いを育てる組織は、変化への適応力が高くなります。
⸻
第4章|経営判断の迷いに向き合うための3つの問い
経営判断に迷ったとき、以下の3つの問いが有効です:
①「本当にこの選択肢しかないのか?」
→ 代替案の探索を怠っていないか?視野を狭めていないか?
②「これは誰のための決断なのか?」
→ 会社のためか?顧客のためか?自己保身ではないか?
③「5年後、同じ問いをしていたら、自分はどう思うか?」
→ 今この瞬間の判断が、長期的に納得できるものか?
これらはすべて、経営の“軸”を確認する問いです。
ソクラテスのように、「問いによって思考の深度を上げる」ことが、ぶれない経営判断を支えます。
⸻
第5章|“問いを武器にする会社”になるために
“問いを武器にする会社”とは、社員が「なぜそれをやるのか?」を考え抜ける組織です。
そのためには以下のような環境整備が求められます:
•リーダー自身が“問う姿勢”を見せる
•会議に「問いの時間」を設ける
•問題発見型の人事評価を導入する
問いを持った社員は、自走し始めます。
指示待ちではなく、“意味”を問いながら判断できる人材こそが、次の時代を切り拓くのです。
⸻
まとめ
「知らないということを、知っている」――それが、ソクラテスが生涯をかけて伝えたことでした。
経営においても、絶対的な正解など存在しません。
そのなかで、何を問うか、誰と問うか、問い続けられるかが、企業の未来を左右します。
問い続ける姿勢は、経営の“軸”をつくり、社員の“考える力”を引き出します。
それが、ソクラテスから私たちが受け継ぐべき、最も実践的な“哲学”なのです。
⸻
次の一歩は、経営者としての“問い”を持つことから。
「我が社は、いま営業組織をどう進化させるべきか?」
その問いに、私たちは共に向き合います。
30分の無料戦略相談で、現状の可視化と次のアクションを見つけてください。