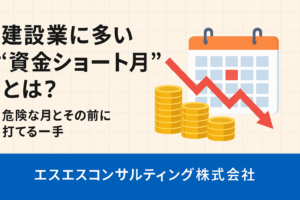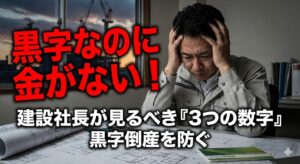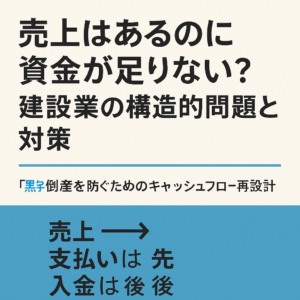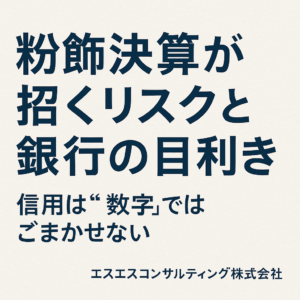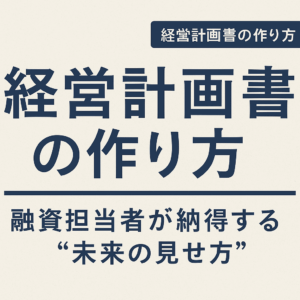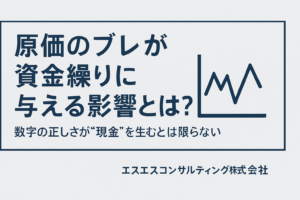月次試算表で経営が変わる!銀行も信頼する財務管理術 3
2025年8月14日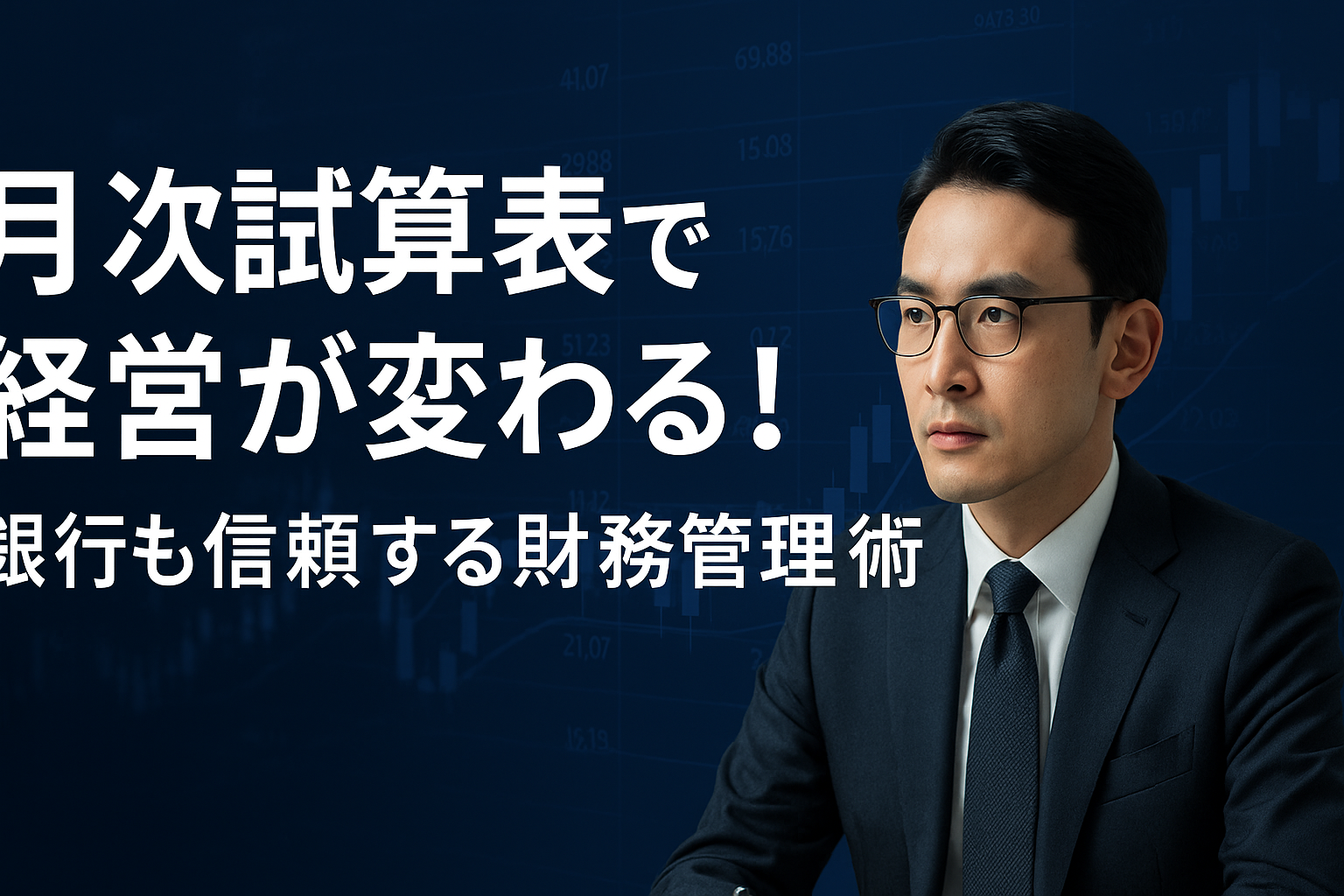
月次試算表で経営が変わる!銀行も信頼する財務管理術
― 経営判断を「感覚」から「データ」へ。見える化がもたらす資金戦略の進化 ―
はじめに|なぜ「月次試算表」が経営の未来を左右するのか
多くの中小企業が、「売上はあるのに資金が足りない」という矛盾に直面しています。
その根本要因の一つが、「数字に基づく経営判断の欠如」です。
財務データを、単なる“会計処理の結果”として捉えるか。
それとも、“未来を設計するツール”として活用するか。
その差が、事業の存続可能性を左右します。
1. 月次試算表とは何か?その定義と役割
月次試算表とは、毎月の損益状況と財務状況を明らかにする帳票です。
要するに、「会社の健康診断書」を毎月発行するイメージです。
試算表の3つの基本構成:
- 損益計算書(P/L):売上・利益・経費構造
- 貸借対照表(B/S):資産・負債・純資産の構成
- 資金繰り表(C/F):キャッシュの実態
2. 経営に「数字文化」が根づかない理由
日本の中小企業には、「どんぶり勘定文化」が根づいており、財務を“感覚”で捉える傾向があります。
| 項目 | 外資系企業 | 日系中小企業 |
|---|---|---|
| 経営会議の資料 | KPI・財務指標中心 | 定性的な報告が多い |
| 意思決定の根拠 | ロジック・数値 | 感覚・経験 |
| 評価指標 | EBITDA・ROICなど | 売上・粗利中心 |
3. 銀行は試算表の“どこ”を見ているのか
- 売上の安定性と利益率の推移
- 短期借入金の依存度と返済能力(DSCR)
- 資金繰りの安定性(フリーキャッシュフロー)
- 債務超過の兆候 or 黒字転換のサイン
銀行にとって、「試算表の鮮度」=信頼の指標です。
4. 数字から“逃げる経営者”の心理構造
数字を「苦手だから」と遠ざけてしまう経営者は、少なくありません。
しかし、その姿勢が黒字倒産リスクを招くのです。
数字は敵ではなく、未来を守る“パートナー”です。
5. 月次試算表で変わる、組織と意思決定
- 社員との共通言語が「数字」になる
- 投資判断が感覚からロジックへ進化
- 営業会議が「利益会議」に変わる
月次試算表は、企業文化そのものを変える「OS(Operating System)」です。
6. 「未来予測ツール」としての試算表運用法
以下の4ステップで、経営のレーダーに昇華させましょう。
- 月次10日以内に試算表を出力
- P/L、B/S、C/Fをセットで確認
- 役員・管理職でレビュー会議を実施
- KPI連動型のPDCAを四半期で運用
7. まとめ|数字は嘘をつかない。だが、人は数字を裏切る
試算表を「作る」ことが目的ではありません。
「活用して意思決定を変える」ことにこそ、真の価値があります。
数字に強い会社は、どんな逆風にも立ち向かえます。
今日から、月次試算表を「未来の羅針盤」として活用しましょう。
\無料診断・資料請求はこちら/
▶ 月次試算表テンプレート付き!財務改善の無料相談受付中