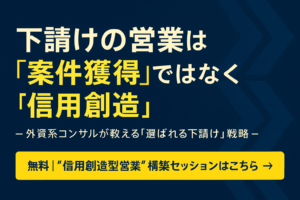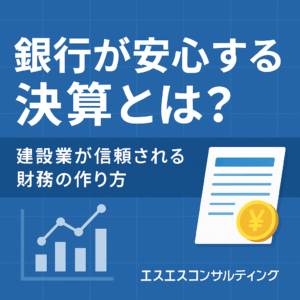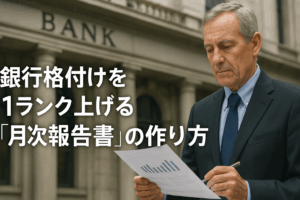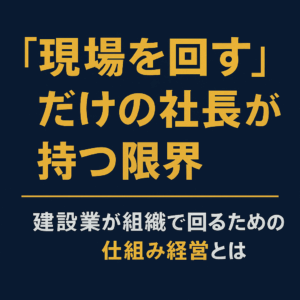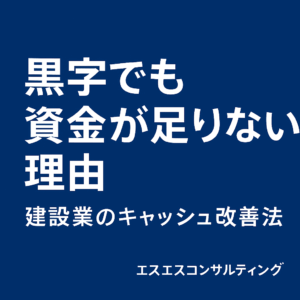建設業の資金が減る原因は“原価の遅れ”にある|改善の仕組みとは
2025年11月10日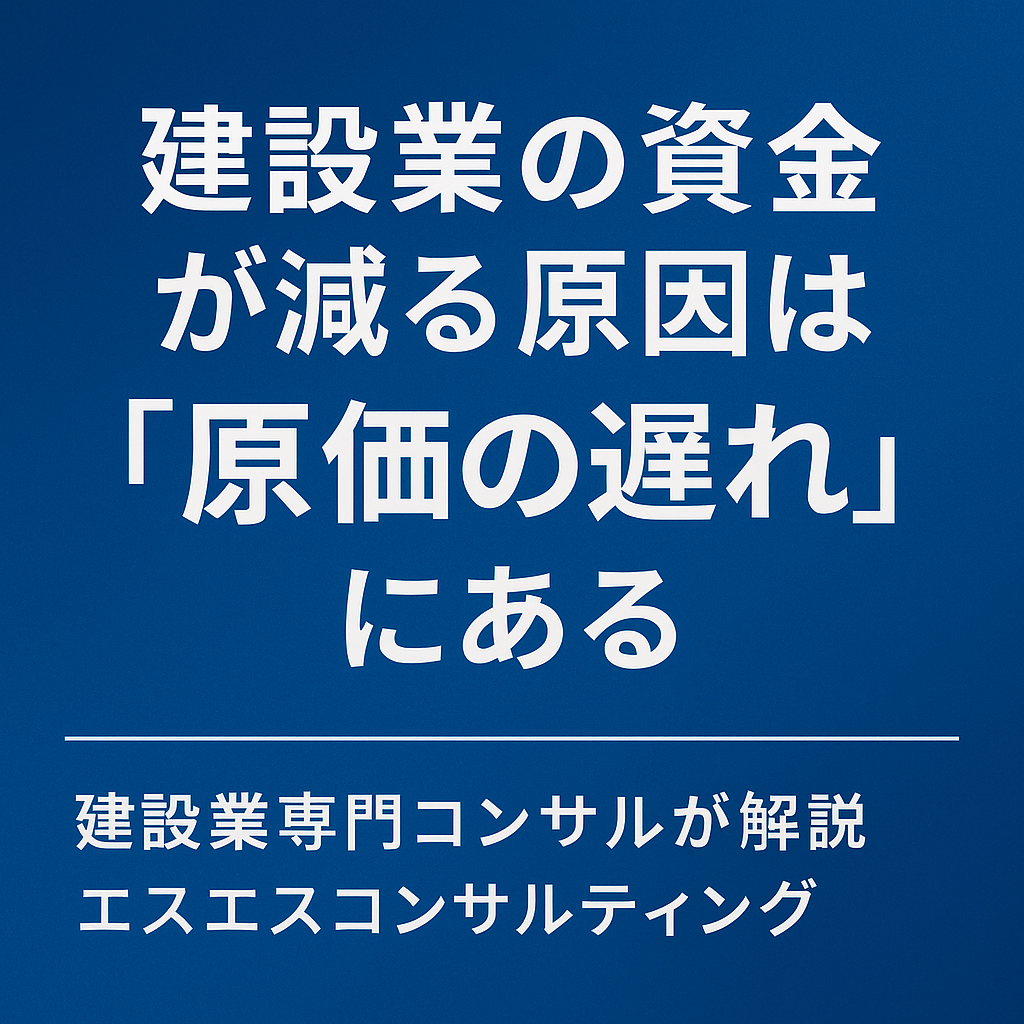
1. 原価の遅れが資金を減らすメカニズム
| 要因 | 内容 | 資金への影響 |
|---|---|---|
| 出来高の遅れ | 進捗報告が遅れ、売上計上が翌月以降にずれ込む | 入金が後倒しになり資金ギャップ拡大 |
| 検収遅れ | 外注・材料費が確定せず、未払計上がズレる | 実態よりも資金残が多く見える(錯覚) |
| 未成工事支出金 | 仕掛金が長期化し、資金が“倉庫”に滞留 | 利益は出てもキャッシュが不足 |
資金繰り悪化は「利益不足」ではなく「原価情報の遅れ」が原因であることが多い。
2. 改善の第一歩:原価の“早期化”
資金を守るには、原価を早く確定させる仕組みが必要です。具体的には、
- 毎月10日締めの出来高報告
- 未検収分は“見積計上”で前倒し
- 証憑管理をクラウド化(発注番号・PJコード紐付け)
「見積計上→翌月リバース」方式により、スピードと精度を両立できます。
3. 管理会計で“原価の遅れ”を見える化
月次での粗利分析をプロジェクト単位で可視化することで、どの現場が遅れているかを即座に把握できます。
| プロジェクト | 進捗率 | 原価確定率 | 差異 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| A現場 | 80% | 65% | -15% | 出来高報告遅延 |
| B現場 | 50% | 50% | ±0% | 正常 |
| C現場 | 60% | 40% | -20% | 外注検収待ち |
4. “原価の遅れ”を無くす仕組み構築ステップ
- 現場・工務・経理の責任区分を明文化(締日・提出期限を固定)
- 出来高報告・検収報告のフォーマット統一
- 工事台帳と会計システムをPJコードで連動
- 月次ミーティングで差異分析(粗利率△3ptを赤信号化)
建設業の資金繰り改善は「スピード×構造」。現場から数字が10日で上がる仕組みを作ることが最重要です。