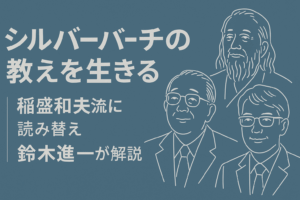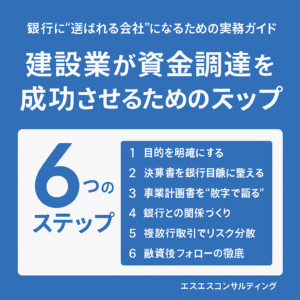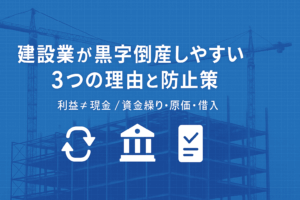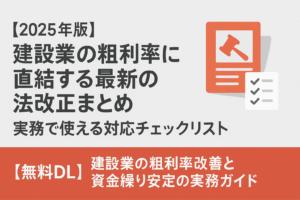建設業における「労働の意味」を再定義する哲学的経営論
2025年7月20日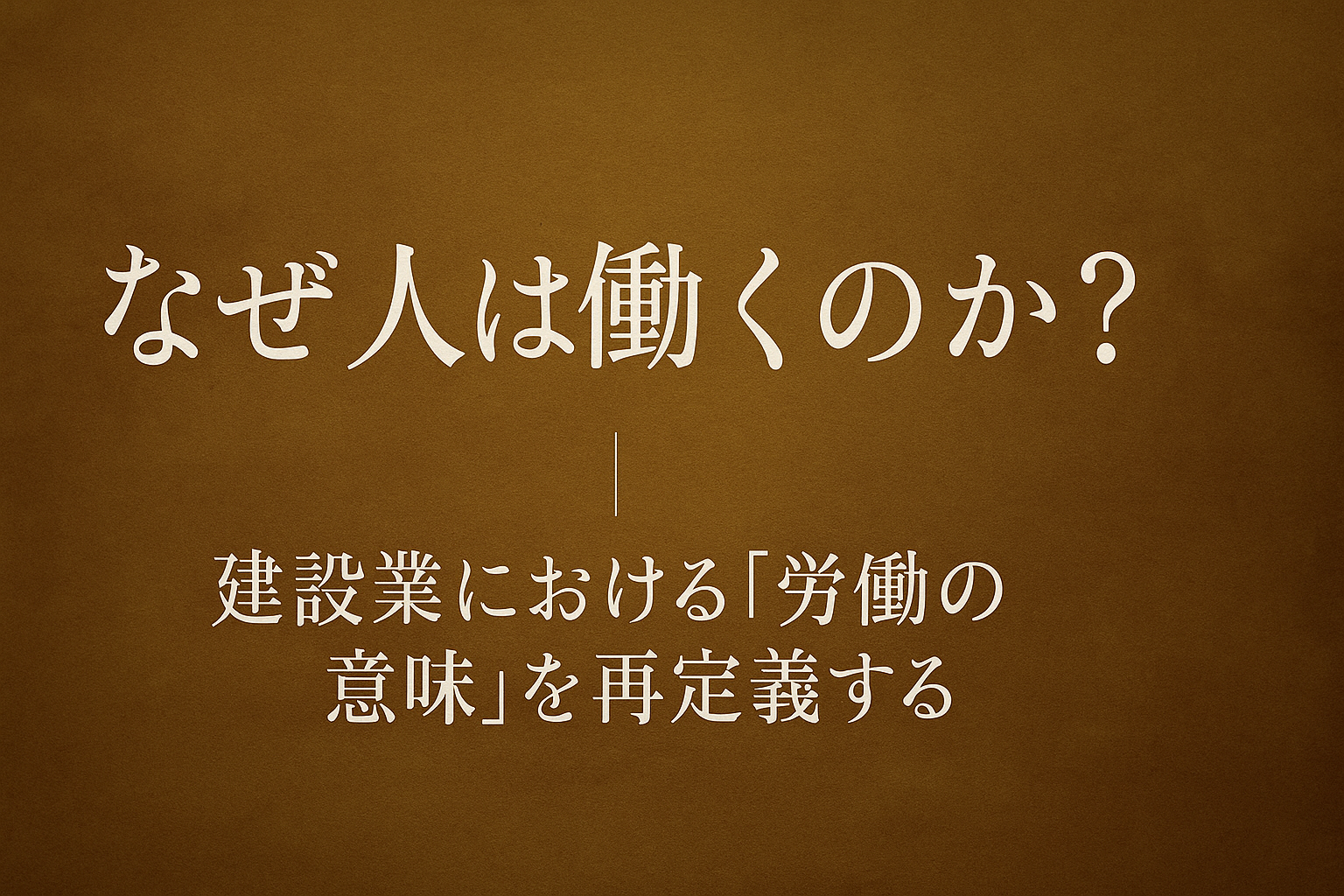
はじめに|エスエスコンサルティングの鈴木です
「働く意味って、なんですか?」
この問いに、即答できる人は少ないでしょう。
でも誰もが、朝早く起きて、満員電車に乗り、現場に向かい、汗を流し、夜にはくたくたになって帰ってくる。
それを、週5日、1年のほとんど繰り返している――。
果たしてそれは、何のためか?
本記事は「建設業の経営者」「現場で働く人」「未来の働き方を模索する人」へ向けて、“働く”という行為そのものの意味を問い直す長編思考録です。
人はなぜ働くのか?
そして、経営者はどう「働く意味」をつくるのか?
哲学・歴史・現場のリアルを交差させて、1万字で読み解いていきます。
⸻
第1章|「働く意味」はどこにあるのか?
1-1. 表面的な理由:「生活のため」では足りない
「働く理由」を聞くと、多くの人はこう答えます。
•家族を養うため
•ご飯を食べるため
•生活費を稼ぐため
これらはすべて「目的」ではなく「手段」です。
生活費を得ることは働く“結果”であって、働く“意味”や“意志”ではないのです。
1-2. 働く意味が見えなくなると、心が壊れる
•若手が続かない
•中堅が疲弊している
•ベテランが無気力になっている
現場ではこうした悩みが深刻化していますが、給与や休日の改善だけでは本質的な解決にはなりません。
なぜなら、「人は意味を感じられないと、動き続けることができない」からです。
⸻
第2章|人間の歴史と「労働観」の変遷を辿る
2-1. 古代ギリシャ|労働は“自由を奪う罰”
哲学者アリストテレスにとって、労働は下層民や奴隷のものでした。
真の人間の営みは「考えること」であり、「手を動かすこと」は“自由から遠ざかる”行為だったのです。
2-2. キリスト教世界|労働は“神の試練”
中世に入り、労働は“罪深い人間が罰として背負うべきもの”と位置づけられました。
「働くことは尊いことだが、楽ではあってはならない」――という宗教的価値観が支配していたのです。
2-3. 産業革命〜現代|労働は“商品化”される
産業革命以降、人間の労働力そのものが「売り買い」されるようになりました。
この結果、人は“何をしているか”よりも“いくら稼いでいるか”で評価されるようになります。
⸻
第3章|現代日本の労働現場にある“無意味感”
3-1. 「働いても報われない」という声
「がんばっても給料は変わらない」
「真面目にやるほど損をする」
「誰も自分の仕事を見ていない」
こうした声が現場から上がるのは、働く意味が“社会的承認”と接続していないからです。
3-2. 管理職・経営者もまた「意味の空白」に苦しんでいる
•「人材が定着しない」
•「やりがいを与えたいが、方法が分からない」
•「そもそも自分は、なぜ経営しているのか…?」
これは、社員の問題ではなく、構造の問題です。
働く意味を“与えられるもの”ではなく“共につくるもの”として捉える必要があります。
⸻
第4章|哲学が教える「働く意味の再構築」
4-1. アリストテレスの目的論:「すべての行動には目的がある」
アリストテレスによれば、人間の究極的な目的は**幸福(エウダイモニア)**です。
働くこともまた、その幸福に向かう“プロセス”でなければならない。
たとえば:
•技術が高まる喜び(自己実現)
•現場で役立つ実感(貢献感)
•仲間との信頼(共同体感覚)
これらが揃って初めて、「働くことが意味を持つ」のです。
⸻
4-2. ハイデガーの“現存在”|ただの作業ではなく「意味のある関わり」
哲学者ハイデガーは、人間を「現存在(ダス・ザイン)」と定義しました。
つまり、“ただそこにいる存在”ではなく、意味を問い、世界と関わる存在だということです。
「この現場での自分の存在が、何かを支えている」と実感できるかどうか――
それが、仕事に魂が宿るかどうかの分かれ目です。
⸻
4-3. カール・マルクス|労働の疎外とは何か?
マルクスは、資本主義社会において「労働が人間から奪われていく現象」を指摘しました。
それは以下の4つの疎外です:
1.労働の産物からの疎外(自分が作ったものが自分のものではない)
2.労働過程からの疎外(作業が自動化し、人間性が失われる)
3.人間の本質からの疎外(働くことが“生きること”と乖離する)
4.他人からの疎外(競争によって分断される)
この“疎外”を乗り越えるには、「自分の仕事が、誰かの役に立っている」と実感できる設計が必要です。
⸻
第5章|建設業の現場に“意味”を取り戻す実践法
5-1. 社長が「言語化」することから始まる
•なぜこの業種を選んだのか
•どんな未来をつくりたいのか
•社員にどんな人生を歩んでほしいのか
このような問いに、社長自身が答えを持ち、語れるかどうか。
それが“意味のある組織”の第一歩です。
⸻
5-2. 目の前の作業に“物語”を与える
「足場を組む」という行為を「命を守るための装備」として語る。
「重機の整備」を「地域の安全を守る備え」として伝える。
これは言葉遊びではなく、価値の再定義です。
作業が“物語”を持った瞬間、仕事は“意味”に変わります。
⸻
5-3. 評価制度に「価値」を組み込む
売上・利益だけでなく:
•後輩指導
•段取り力
•施工品質
•顧客からの声
こうした“定量化しづらい貢献”を評価に入れることで、人は報われると感じられるようになります。
⸻
第6章|働く意味を見出したとき、人は変わる
•残業が苦にならなくなった
•朝早く来るようになった
•新人を自分から育てるようになった
こうした変化は、「働く意味を感じられた人」に起こる行動変容です。
人は、“納得して動く”とき、最も強く、最も自律的になります。
⸻
第7章|「働く意味」を組織全体で共有するための仕掛け
7-1. “理念の押しつけ”ではなく“対話”から始める
経営者が語るビジョンやミッションは重要ですが、それを一方的に掲げるだけでは社員には響きません。
大切なのは、社員一人ひとりが「自分の言葉」で語れるようになること。
「あなたにとって、仕事の意味とは何ですか?」
この問いに、社員が5分以上話せるようになることが、理念浸透の本当の成果です。
⸻
7-2. ワークショップ・面談・1on1で“意味の翻訳”を
現場では、日々の忙しさで仕事の目的を見失いがちです。
その中で、定期的に「内省の場」を設けることが重要です。
▷ 具体例
•月1回の1on1面談で「働く意味」について語る時間を3分入れる
•朝礼で「最近誇りを感じた仕事」について共有する習慣をつくる
•経営理念を現場の仕事に翻訳した“業務別ミッションカード”を作る
⸻
7-3. 意味が共有されると、現場はどう変わるか?
•作業が「ただの作業」から「責任ある仕事」になる
•トラブル対応でも「俺の責任じゃない」ではなく「チームの課題」になる
•後輩指導に「面倒くさい」ではなく「継承すべき技術」という意識が芽生える
働く意味が浸透した現場は、**管理しなくても機能する“自律型チーム”**になります。
⸻
第8章|採用・定着・育成にも「働く意味」が不可欠
8-1. 給与よりも“ここで働く理由”を求めている若者たち
令和世代の採用においては、
「この会社に入る意味」
「自分が成長できる実感」
「将来の展望」
といった**“物語”と“共感”が鍵**です。
→ 単なる待遇や条件ではなく、「なぜこの仕事をやるのか?」を丁寧に伝える採用設計が必要です。
⸻
8-2. 定着率は“意味”と“承認”で決まる
人は、意味のある場所に居続け、
意味を感じられない場所からは、どんなに高給でも去っていきます。
•感謝される
•成長を感じる
•誰かの役に立っていると思える
•社長の想いが伝わってくる
こうした“意味づけ”が、離職防止の本質的な鍵です。
⸻
8-3. OJTでは育たない時代の「意味づけ育成」
育成で最も重要なのは「教え方」ではなく「導き方」です。
つまり、「なぜこれをやるのか?」「何のために存在する仕事なのか?」を常に伝えること。
OJTに“哲学的問い”を組み込むだけで、若手の理解度と意欲は格段に変わります。
⸻
第9章|未来の働き方における「意味資本」の時代
9-1. 「給与」よりも「意味」に価値を置く時代へ
経済成長が鈍化し、人口が減少する日本において、
今後の企業競争力は「意味」を軸にした“意味資本経営”へと移行します。
•どんな目的で存在する会社か
•その会社で働くことで、どんな人間になれるのか
•顧客にとって、社会にとって、どんな貢献をしているのか
“意味”を明確にできない会社は、採用でも評価でも選ばれなくなります。
⸻
9-2. 「建設業こそ哲学的な産業である」という自覚
建設業は、人が生きるために必要な「空間」「構造物」「安全」を支える存在です。
•命を守る足場
•街の未来をつくる基礎
•家族の暮らしを支える設備
この仕事に“誇り”と“意味”を取り戻すことが、業界全体の価値向上にもつながります。
⸻
終章|経営者が“哲学者”になる時代
経営者は、利益を出す存在である前に、意味を問い続ける存在です。
組織に働く意味を与える存在。
社員の人生にストーリーをもたらす存在。
あなたが語る「なぜこの会社をやっているのか」の一言が、
社員の人生を変えるかもしれません。
⸻
【まとめ】
•働く意味とは、“生活のため”を超えた「自己実現・貢献・つながり」
•意味のない仕事は、人を壊す。意味がある仕事は、人を育てる。
•経営者こそが「意味づけの起点」にならなければならない
•組織の強さは、“理念”より“実感”でできている
⸻
おわりに|経営者が「意味の起点」になる
社員に働く意味を見出してほしいなら、まずは社長が、自分の“なぜ”を語ることです。
•なぜこの業界で
•なぜこの会社を守り続け
•なぜ今、ここに立ち続けているのか
その“物語”に、人は共鳴します。
あなた自身が「働く意味の起点」になってください。
それが、組織に魂を通わせる唯一の方法です。
⸻
社員の定着率を上げたい、職人に誇りを取り戻したい、
“働く意味”を組織で共有したいという方は、
エスエスコンサルティング株式会社まで、お気軽にご相談ください。
次の一歩は、経営者としての“問い”を持つことから。
「我が社は、いまどう進化させるべきか?」
その問いに、私たちは共に向き合います。
30分の無料戦略相談で、現状の可視化と次のアクションを見つけてください。