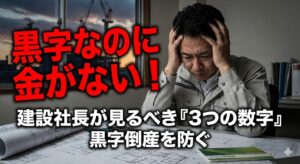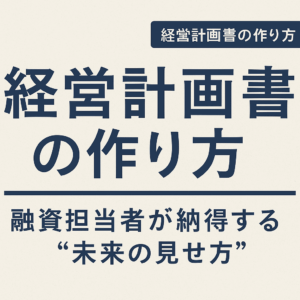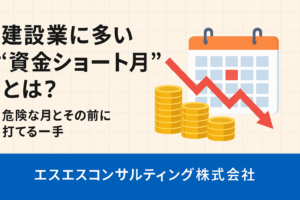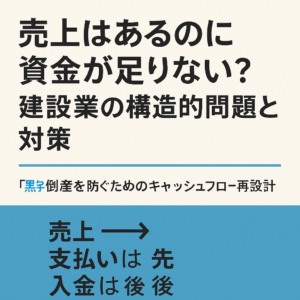原価のブレが資金繰りに与える影響 8
2025年8月19日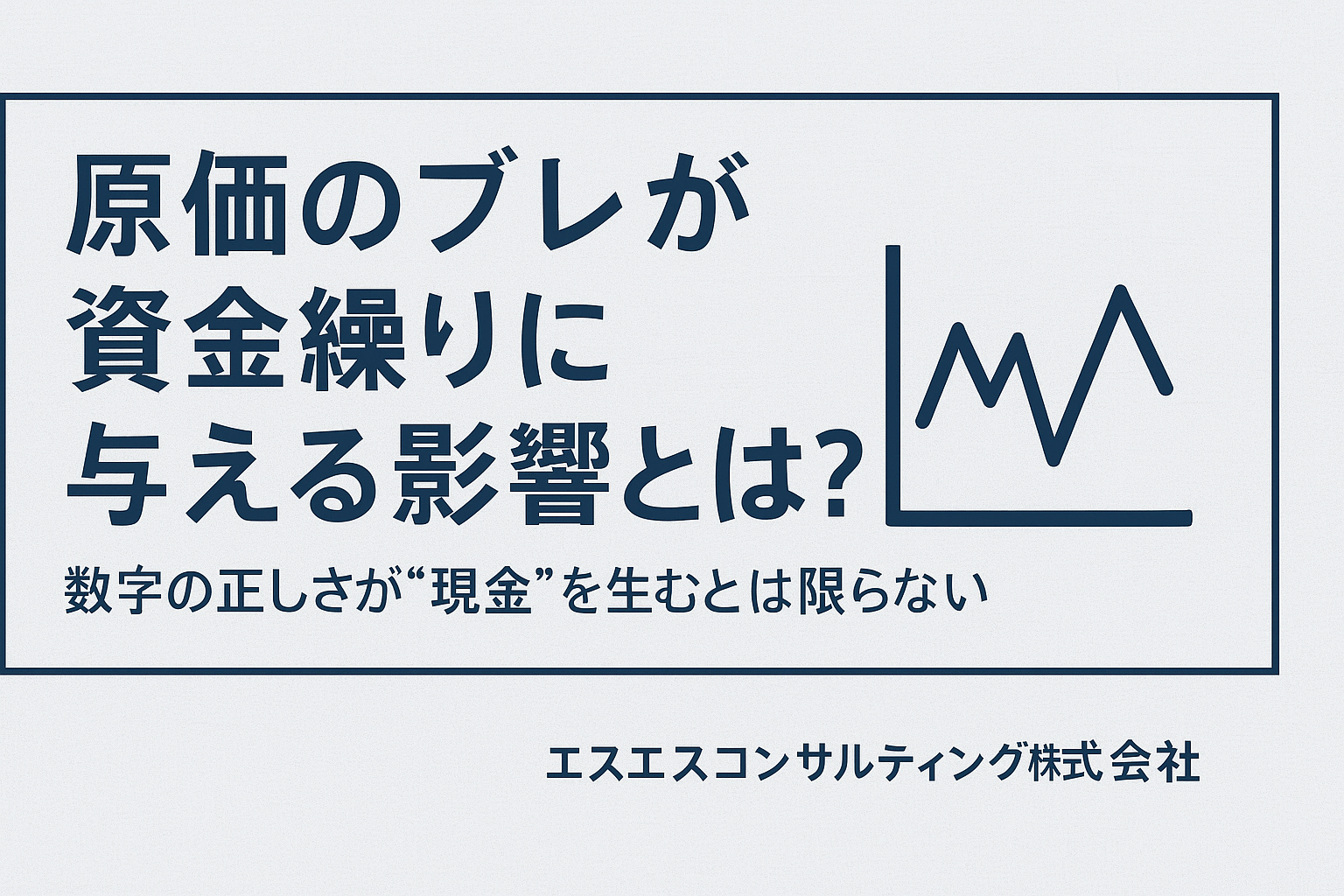
原価のブレが資金繰りに与える影響とは?数字の正しさが“現金”を生むとは限らない
エスエスコンサルティング株式会社|建設業に特化した財務再生のプロフェッショナル
1. 「利益は出ているのに、通帳が減る」の正体
毎月の試算表を見ると黒字。粗利率もまずまず。しかし、月末には銀行口座の残高が底をつく。
「数字上は合っているのに、現金が足りない」というこの現象は、建設業において非常に多くの経営者が経験する“資金ショートの罠”です。
この違和感の背景にあるのが、「原価のブレ」です。
これは会計上の“誤り”ではありません。むしろ帳簿は正しい。
しかし、原価のブレがもたらす資金への波及は、実務と会計の“非対称性”を露呈します。
2. 原価とは“予測”である|過去ではなく未来を見る力
工事原価とは、「工事が完成してみないと確定しない」性質のものです。
つまり、現場が進行している間は、“見積原価”=仮の数字が粗利を構成している状態にあります。
この時点で損益が正確である保証はどこにもありません。
さらに、以下のようなブレが発生するリスクがあります。
- ・外注先が追加請求してきた(見積外費用)
- ・資材価格が急騰した
- ・工期遅延による手待ちコスト
- ・社内ロス(手戻り・手配ミス・管理コスト)
工事原価は“現実”であり、帳簿上の数字は“想定”にすぎません。
このギャップが埋まらない限り、損益とキャッシュは乖離し続けます。
3. 原価のブレは「遅れて」資金を殺す
原価のズレはすぐには資金繰りに表れません。
完成・請求・入金というプロセスがある以上、“損失の自覚”が遅れるのです。
たとえば、以下のような流れがよく見られます。
- ① 工事中:利益予測が出ているので、資金計画も強気
- ② 入金直後:資金が潤うので、仕入れや外注に積極投資
- ③ 数か月後:予期せぬ原価上昇が発覚。実質赤字。
- ④ 翌月:キャッシュ不足→外注費・税金・借入返済が困難に
原価のズレは、まるで“時限爆弾”のように、あとから資金を爆発させます。
4. なぜ原価管理の甘さが慢性化するのか?
経営者が「今月の粗利はいいぞ」と信じる根拠は、たいていの場合、会計ソフトが出す数値か、経理担当者の報告です。
しかしその裏側には、次のような“見えない落とし穴”があります。
- ・進行中工事の実行予算が更新されていない
- ・追加工事が未確定のまま処理されている
- ・完了引渡後の原価清算がされていない
- ・間接費の配賦基準が曖昧
現場感覚と会計上の数字が一致しない組織では、原価のブレは“常態化”します。 そのままでは、資金繰りが「慢性的なズレ」を抱える体質になります。
5. 原価のブレを抑えるために、経営者がすべきこと
① 原価予測の「再評価制度」を設ける
工事ごとに「実行予算の再確認日」を設定し、定期的に見積と実績のズレを精査しましょう。
営業・現場・経理の“三位一体チェック”が重要です。
② 完工後の「工事別キャッシュフロー分析」
売上・原価・利益だけでなく、「工事完了から入金までの現金収支」を記録する文化をつくりましょう。
キャッシュ単位での原価管理ができると、資金繰りが読みやすくなります。
③ “誤差を飲み込める”資金余力の確保
ブレをゼロにするのではなく、ブレても潰れないキャッシュ体質をつくることが最終目的です。
そのためには「固定費1ヶ月分+外注費1ヶ月分」のキャッシュ保有を目標にすべきです。
6. まとめ|数字は「正しさ」より「使い方」で生きる
原価のズレは悪ではありません。問題は、それを“認識しない経営”です。
数字は常に揺らぎます。しかし、揺らぎを許容し、調整し、先読みする力こそが、経営者に求められる「数字との向き合い方」です。
エスエスコンサルティングでは、建設業の原価管理・資金繰り支援において、
会計・現場・金融の3視点からアプローチする独自の支援体制を整えています。
「粗利はあるはずなのに通帳が寂しい」——その違和感、見逃さないでください。