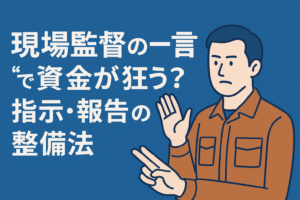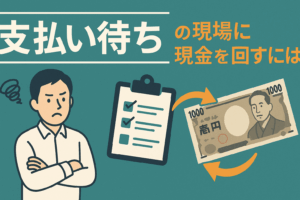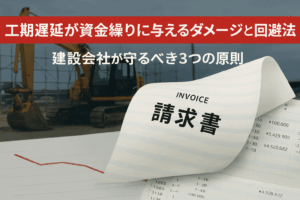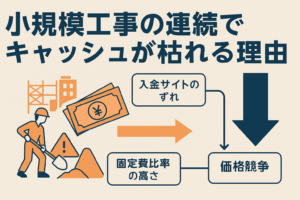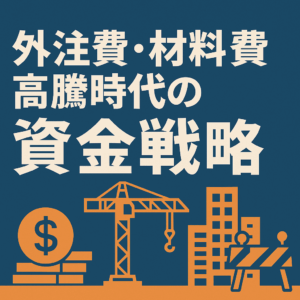借入に強い会社と弱い会社の決定的な違い
2025年10月26日
借入に強い会社と弱い会社の決定的な違い
同じ売上・同じ業種でも、銀行から融資を受けやすい会社と、なかなか融資が通らない会社があります。
この差は、実は「業績」だけで決まるわけではありません。
この記事では、建設業の現場で実際に見てきた「借入に強い会社」と「弱い会社」の決定的な違いを、実践的に解説します。
① 数字で語れる会社は“信用”を得やすい
借入に強い会社の共通点は、自社の数字を自分の言葉で説明できることです。
例えば、決算書を見ながら銀行にこう話せる社長は非常に強いです。
「うちは粗利率が昨年より2%改善しています。理由は職人の手待ちを減らし、原価を見える化したからです。」
一方、数字を会計事務所任せにしている会社は、“経営をコントロールしていない”と見なされ、信用力が低下します。
- 毎月の試算表を社長自身が確認しているか?
- 粗利率・経費率・営業利益率を把握しているか?
- 資金繰り表を作成・更新しているか?
これらができていれば、銀行面談での信頼度は一気に上がります。
② “資金使途”を明確に説明できる会社は強い
借入審査で最も重要なのは、「なぜお金を借りるのか」という明確な理由です。
銀行は「資金使途が曖昧」な会社を最も嫌います。
借入に強い会社は、資金を「未来の利益につなげる」ために使う設計を持っています。
- 新しい元請案件の立ち上げ資金
- 人材採用・教育への投資
- 粗利率改善のための設備・効率化投資
一方で、赤字補填や資金ショート防止のための借入は、融資判断が厳しくなります。
目的が“成長のため”か“延命のため”か、この違いが決定的です。
③ 銀行との“関係づくり”を軽視しない
借入に強い会社は、決して「借りたいときだけ銀行に行く」ことをしません。
定期的に情報共有を行い、信頼を積み上げています。
- 年2〜3回は、決算報告書・試算表を自ら提出している
- 取引先の状況や新しい元請の動きを共有している
- 経営計画を簡潔に説明できる
銀行は“数字”ではなく、“人”を見ています。
「この社長なら大丈夫」と思われることが最大の信用です。
④ 資金繰り表で“未来の数字”を見せられるか
銀行が最も安心するのは、“資金繰りの見通しが立っている会社”です。
試算表や決算書は過去の数字。 しかし、資金繰り表は「未来の経営計画」を示す資料です。
- 毎月の入金予定と支出予定を可視化している
- 借入返済・税金支払いを含めた実残高を管理している
- 「いつ資金が不足するか」が予測できる
この管理ができていれば、銀行は「この会社は資金管理ができている」と評価します。
⑤ 借入後のフォローを怠らない
融資が実行された後にこそ、信頼を積み上げるチャンスがあります。
借入に強い会社は、借りっぱなしにせず“使い方と成果”を報告します。
「先日いただいた融資で新しい設備を導入し、原価率が2%下がりました。」
この一言で、次の融資のハードルが下がります。
銀行は“お金を回収できる相手”ではなく、“一緒に成長できるパートナー”を求めています。
まとめ:借入力=経営力の見える化
借入に強い会社は、決して特別なコネや運を持っているわけではありません。
「数字で語り、目的を示し、信頼を積み重ねる」——この3つを実行しているだけです。
今後の借入・資金調達を有利に進めたい方は、まず自社の財務体質と銀行との関係構築を見直してみましょう。
「下請けの味方」では、
銀行格付けの改善・資金繰り表の設計・借入交渉の戦略立案まで、金融機関に強い経営体制をサポートしています。