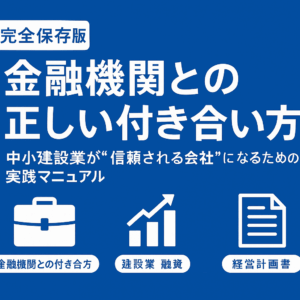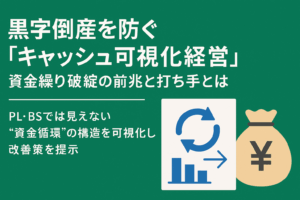中小建設業が銀行評価を上げるには?信用格付のロジックと逆転戦略 銀行の“評価視点”を分解し、逆算で改善するアプローチとは?
2025年7月6日
はじめに|エスエスコンサルティングの鈴木です
銀行は中小建設業をどう評価しているか?
建設業は他の業種と比べて、銀行から「リスクが高い」と評価されがちです。理由は以下の通りです:
•受注が単発で不安定
•回収サイトが遅く、資金繰りがタイトになりやすい
•原価が不安定で、利益率が読みづらい
また、銀行は「人柄」ではなく「数字と実績」で評価するため、感覚的な交渉は通用しません。
⸻
信用格付のロジックと2つの評価軸
銀行が企業に対して与える「格付」は、融資判断や金利条件に直結する重要な指標です。
この格付は次の2軸で決定されます。
◆ 定量評価(6割程度)
•営業利益率
•自己資本比率
•債務償還年数(借入金返済年数)
•売上増減、経常利益の安定性など
◆ 定性評価(4割程度)
•経営者の資質と経験
•業界でのポジション
•主要取引先の安定性
•経営計画の有無と妥当性
銀行はこの2軸を使い、100点満点の格付スコアを算出します。
⸻
銀行評価を落とす3つの落とし穴
評価が下がる中小企業には、共通する“落とし穴”があります。
❌ ① 利益が出ていても債務償還能力が低い
「利益は出ているのに評価が低い…」というケースは、借入が多くて返済能力が低いパターンです。
❌ ② 自己資本がほぼゼロ
資本金や利益剰余金がない場合、「いつ潰れてもおかしくない」と見なされます。
❌ ③ 経費の私的流用・役員貸付がある
役員貸付金や、私用のクレジットカード使用などは、経営者への信用喪失に直結します。
⸻
格付逆転の「評価逆算経営」ステップ
では、どうすれば格付を上げられるのか?
答えは“逆算”です。
✅ Step1|財務3指標の目標を設定
•自己資本比率:30%以上
•営業利益率:5%以上
•債務償還年数:5年以内
✅ Step2|数値改善のアクションを明確化
•粗利を確保する受注選別
•不要借入の整理と返済優先
•税理士と連携して透明な決算を作る
✅ Step3|「見せ方」の工夫で定性評価を上げる
•経営計画書を作成し提出
•月次の試算表や資金繰り表を銀行に定期提示
•担当者との情報共有を継続する
⸻
銀行との付き合い方で資金調達力が変わる
銀行担当者との関係性が薄い企業ほど、審査は冷淡です。
以下を実践することで、金融機関からの信頼を高めましょう。
•決算だけでなく、期中の業況報告を行う
•月次決算書や進捗レポートを定期的に提出
•雑談や日々の連絡で“顔が見える経営者”を意識する
⸻
まとめ|信用格付は“見せ方”と“数字の積み重ね”で変えられる
銀行評価は、属人的な交渉ではなく、「数字」と「信頼」の積み重ねでしか動きません。
しかし、その逆算ロジックさえ押さえれば、必ず改善の道は拓けます。
⸻
次の一歩は、経営者としての“問い”を持つことから。
「我が社は、いまどう進化させるべきか?」
その問いに、私たちは共に向き合います。
30分の無料戦略相談で、現状の可視化と次のアクションを見つけてください。