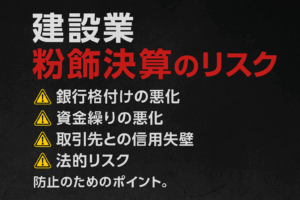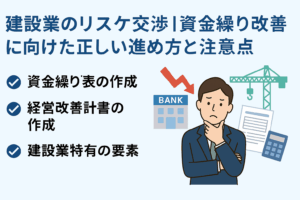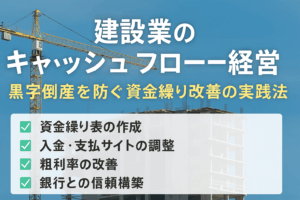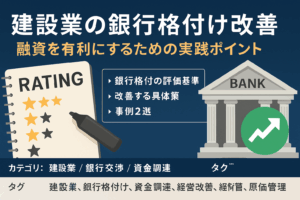ファクタリングに依存すると会社が危うい?建設業の失敗事例と対策
2025年9月12日
建設業におけるファクタリングのデメリットとは?|資金繰り改善の落とし穴
🏗 なぜ建設業でファクタリングが注目されるのか?
建設業は請負契約の特性上、工事完了から入金までの期間が長く、資金繰りのタイムラグに悩まされやすい業界です。 特に下請け企業は「月末の支払いが迫っているのに元請からの入金は先」という状況が頻発します。 その解決策のひとつがファクタリング(売掛金の早期現金化)です。
しかし、ファクタリングは便利な反面、多くのデメリットも存在します。以下に詳しく解説します。
⚠️ 建設業におけるファクタリングの主なデメリット
1. 高額な手数料
ファクタリングの手数料は5〜20%が一般的です。 銀行融資の金利と比べて非常に高く、粗利率の低い工事では利益が消えてしまうこともあります。
2. 利用できる請求書に制限がある
公官庁案件や大手ゼネコン相手の請求書は審査が通りやすいですが、 中小元請や個人顧客の案件では利用できない場合があります。 「必要な案件が対象外」というリスクがあるのです。
3. 取引先との信頼関係悪化リスク
2社間ファクタリングであっても、ファクタリング会社が入金確認を行うため、 元請に知られる可能性があります。 「資金繰りに困っている会社」と思われ、信用低下につながる危険性があります。
4. 根本的な解決にはならない
ファクタリングはあくまで「入金の前倒し」であり、 慢性的な資金繰り改善には直結しません。 継続利用すると高コスト体質になり、かえって資金を圧迫します。
5. 悪質業者によるトラブル
ファクタリングは登録制度が未整備なため、悪質業者が存在します。 高額手数料を要求されたり、貸金業まがいの契約でトラブルになるケースも報告されています。 契約時は必ず信頼できる事業者を選ぶことが重要です。
6. 税務・会計への影響
ファクタリングは「売掛金の譲渡」として処理しますが、 契約によっては「実質的な借入」と判断されるリスクもあります。 その場合、銀行の信用評価(格付け)に悪影響が及ぶ可能性があります。
✅ 建設業における資金繰り改善の代替策
- 銀行融資: 金利が低く、中長期的な資金調達に有効
- 補助金・助成金: 返済不要の資金で、DX投資や人材育成に活用可能
- 原価管理の徹底: 粗利率改善によるキャッシュフロー強化
- 請求・回収体制の整備: 請求漏れ・遅れを防ぎ、資金化を早める
🔍 まとめ
ファクタリングは一時的な資金繰り改善には有効ですが、 高コスト・信用リスク・短期的対処にとどまるという重大なデメリットを抱えています。 利用は「緊急時の資金確保」に限定し、長期的には融資・補助金・原価管理の徹底といった 持続可能な経営改善策を優先すべきです。
📩 建設業の資金繰り改善・補助金活用はお任せください
エスエスコンサルティングは、建設業専門の管理会計・資金繰り改善コンサルティングを提供しています。
ファクタリングに依存しない経営基盤づくりをサポートします。