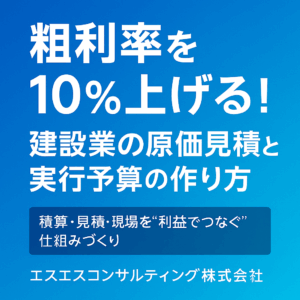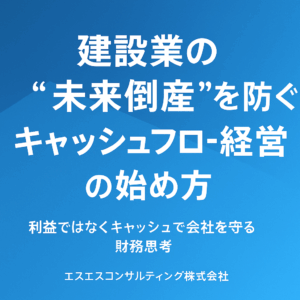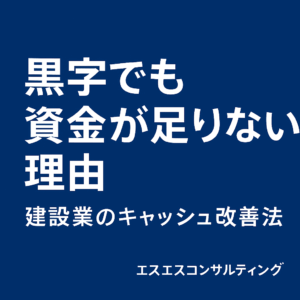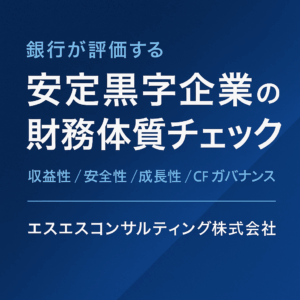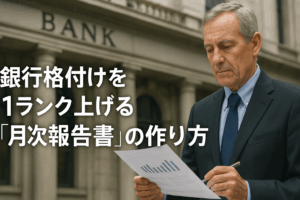『税理士任せ』の限界。管理会計と財務会計の違いを経営者向けに解説
2025年10月22日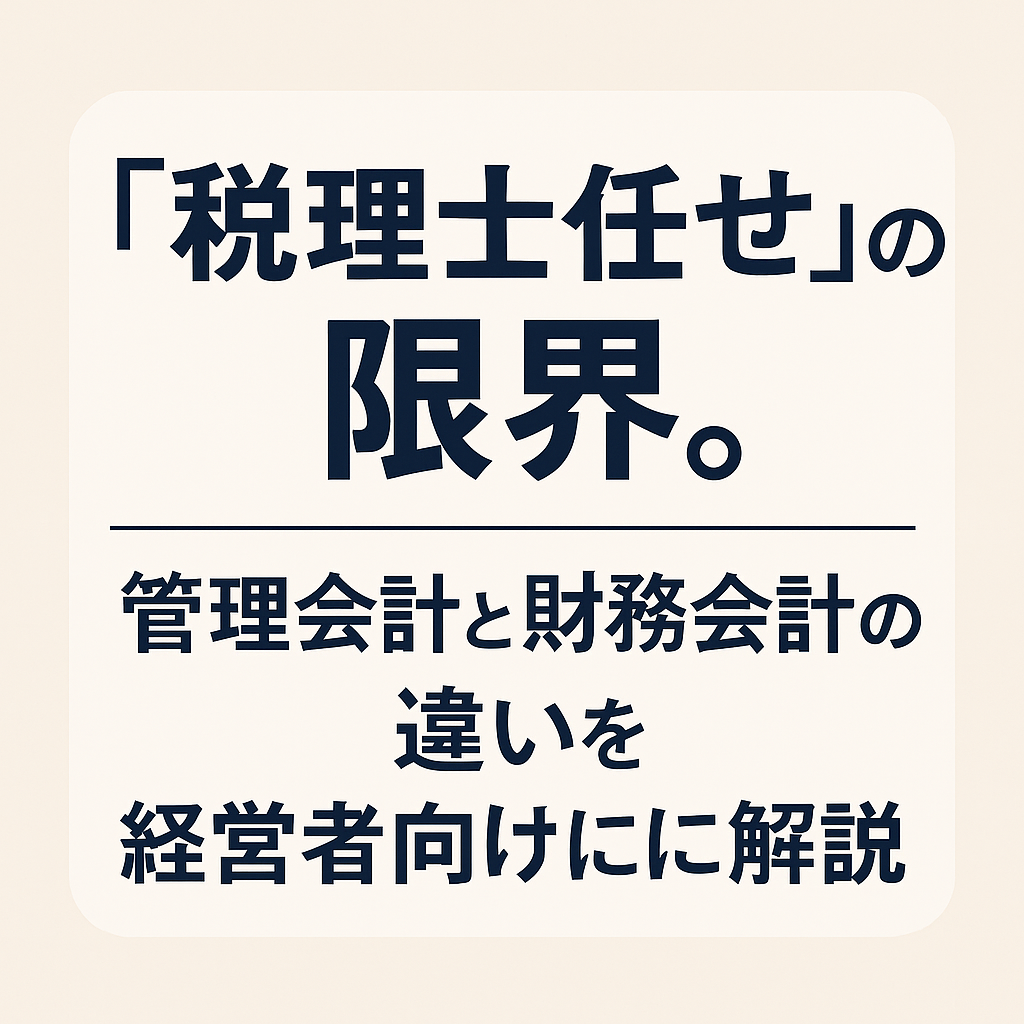
『税理士任せ』の限界。管理会計と財務会計の違いを経営者向けに解説
税金対策ではなく「経営判断のための会計」へ。
建設業が次のステージへ進むために必要な“数字の使い方”を解説します。
1. 管理会計と財務会計の本質的な違い
| 項目 | 財務会計 | 管理会計 |
|---|---|---|
| 目的 | 外部報告(税務署・金融機関) | 内部管理(経営判断・意思決定) |
| 作成者 | 税理士・会計事務所 | 経営者・経営企画・管理部門 |
| タイミング | 年1回(決算後) | 毎月・毎週(リアルタイム) |
| 内容 | 過去実績(損益・資産負債) | 未来計画(利益・資金繰り・原価構造) |
| 重視点 | 正確性・税務整合性 | スピード・意思決定精度 |
つまり、財務会計は「外に見せる会計」、管理会計は「中で使う会計」です。 経営判断を“勘”から“数字”に変えるためには、管理会計が不可欠です。
2. 『税理士任せ』の限界とは
- 決算が終わってから利益を知る ― 対策が打てない。
- 部門別・現場別の粗利がわからない ― 赤字現場の把握が遅れる。
- 月次試算表が遅い ― 経営判断が常に1〜2か月遅れ。
- 銀行との格付け説明ができない ― 数字の「意味」を語れない。
決算書を「作る」ことは税理士の仕事。
しかし、決算書を「使いこなす」ことは経営者の責任です。
しかし、決算書を「使いこなす」ことは経営者の責任です。
3. 経営者が管理会計を導入するメリット
- ① 粗利率の見える化:現場・担当別で採算を分析し赤字を即把握。
- ② 資金繰りの安定化:キャッシュフロー予測を週次で更新。
- ③ 銀行格付けアップ:月次決算の信頼性が融資査定に直結。
- ④ 経営スピード向上:勘定科目・原価データをリアルタイム分析。
4. 建設業における導入3ステップ
- Step1:勘定科目の整理と部門別原価の区分。
- Step2:月次決算体制を構築(経理と現場の連携フロー作成)。
- Step3:KPIダッシュボード(粗利率・案件別採算・資金繰り)を運用。
これにより、毎月の経営会議で「数字に基づく意思決定」が可能になります。
5. 成功事例:粗利率18%→25%に改善したA社
| 項目 | 導入前 | 導入後(1年後) |
|---|---|---|
| 粗利率 | 18% | 25% |
| 決算確定まで | 3ヶ月遅れ | 翌月10日締め |
| 赤字現場の早期発見 | 平均2ヶ月遅れ | リアルタイム把握 |
| 銀行格付け | 6 | 8(借入金利0.5%下落) |
6. まとめと次のアクション
税理士任せの財務会計だけでは、会社の未来は見えません。 経営を数字で“設計”する管理会計を導入することで、 利益構造の改善・資金繰り安定・銀行交渉力アップを実現できます。
エスエスコンサルティングでは、建設業専門の管理会計導入支援を行っています。
現状の決算書から課題を診断し、90日で“使える月次体制”を構築します。
無料経営診断を予約する