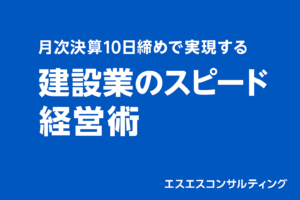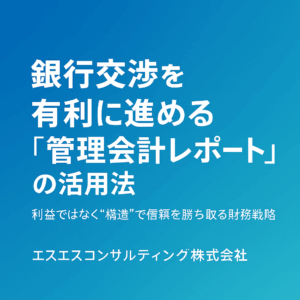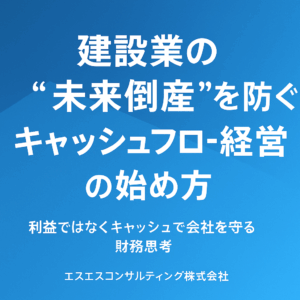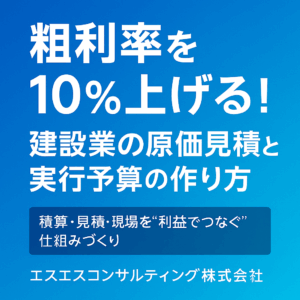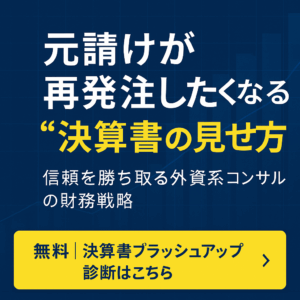「粗利率改善に効く!管理会計の実践ステップ」第2回
2025年9月25日
建設業で粗利率がなかなか改善しない――その原因は「管理会計の仕組み不在」にあります。本記事では、粗利率改善のために役立つ管理会計の考え方と導入ステップを、実際の建設会社の事例を交えて解説します。
なぜ粗利率が改善しないのか?
建設業界の多くの会社で「売上はあるのに、利益が思うように残らない」という声を耳にします。
その原因は次のようなものです:
- 工事ごとの損益が正確に把握できていない
- 見積段階での利益シミュレーションが甘い
- 外注費・材料費の変動を管理できていない
- 現場監督が「粗利意識」を持てていない
つまり、「数字を現場に落とし込む仕組み」=管理会計が存在しないことが、粗利率低下の最大の要因なのです。
管理会計が粗利率改善に効く理由
財務会計は「会社全体の過去の数字」を整理する仕組みですが、粗利率改善には役立ちません。必要なのは「現場ごと・部門ごとに利益を把握し、未来の意思決定につなげる」管理会計です。
管理会計を導入すると、以下の効果が得られます:
- 工事別の粗利率をリアルタイムで把握できる
- 赤字工事を受注前に回避できる
- コスト削減ポイントを数値で特定できる
- 経営会議の議論が「感覚」から「数字ベース」に変わる
粗利率改善に効く!管理会計の5つの実践ステップ
ステップ1:現状把握
まずは現状を把握します。工事ごとの原価・粗利を過去3年分洗い出し、どの案件が赤字要因となっているかを可視化します。
例えば、売上高は大きいが外注比率が高すぎて利益が出ていない案件が浮き彫りになります。
ステップ2:原価管理の仕組み化
外注費・材料費・労務費を現場別に紐づけて集計する仕組みを構築します。
現場監督が日々の発注・支払いを把握できるようにすることがポイントです。
ステップ3:見積精度の改善
過去データを分析し、見積時点で「最低限必要な粗利率」を設定します。
これにより「利益の出ない価格で受注する」ことを防ぎます。
ステップ4:部門別・現場別損益の定期報告
月次の経営会議で「工事別損益表」を用い、部門ごとに粗利率を確認。
赤字の現場は即座に改善策を検討する習慣をつけます。
ステップ5:改善アクションの継続
データに基づく改善を繰り返すことで、粗利率は着実に向上します。
最初は1〜2%の改善でも、年商10億円の会社なら1,000万〜2,000万円の利益改善につながります。
導入事例:粗利率7%→12%を実現したB社
B社では、管理会計導入前は「現場の勘」で見積・進行を管理していました。その結果、売上は伸びても利益が出ず、資金繰りに悩まされていました。
管理会計導入後は、現場ごとに粗利率を算出し、赤字工事を排除。
さらに採算性の高い案件に集中したことで、粗利率は7%から12%へ改善しました。
数字で見る粗利率改善のインパクト
仮に売上高10億円、粗利率7%の会社が、粗利率を10%に改善した場合――
営業利益は3,000万円増加します。
この増益分を人材育成や新規設備投資に充てれば、さらなる成長基盤が構築できます。
無料相談のご案内
エスエスコンサルティング株式会社では、建設業に特化した管理会計導入支援を行っています。
「粗利率改善」「黒字倒産防止」「資金繰り安定化」を実現したい経営者様は、まずは無料の経営診断をご活用ください。
まとめ
建設業で粗利率を改善するには、「管理会計による仕組み化」が不可欠です。
勘や経験ではなく、数字をベースにした経営判断を実践することで、粗利率は確実に上がり、資金繰りの不安も解消されます。
今こそ、管理会計を導入し、経営の未来を数字で描きましょう。