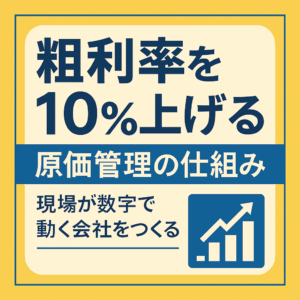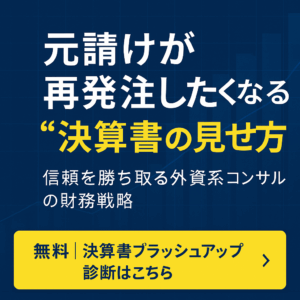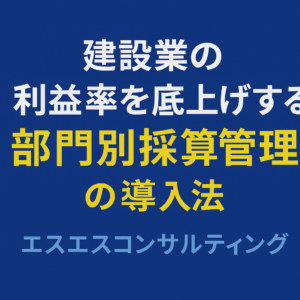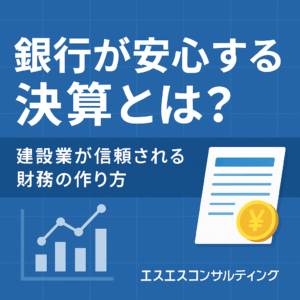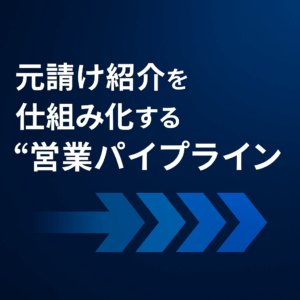「月次決算10日締め」を実現する建設業のスピード経営術
2025年11月9日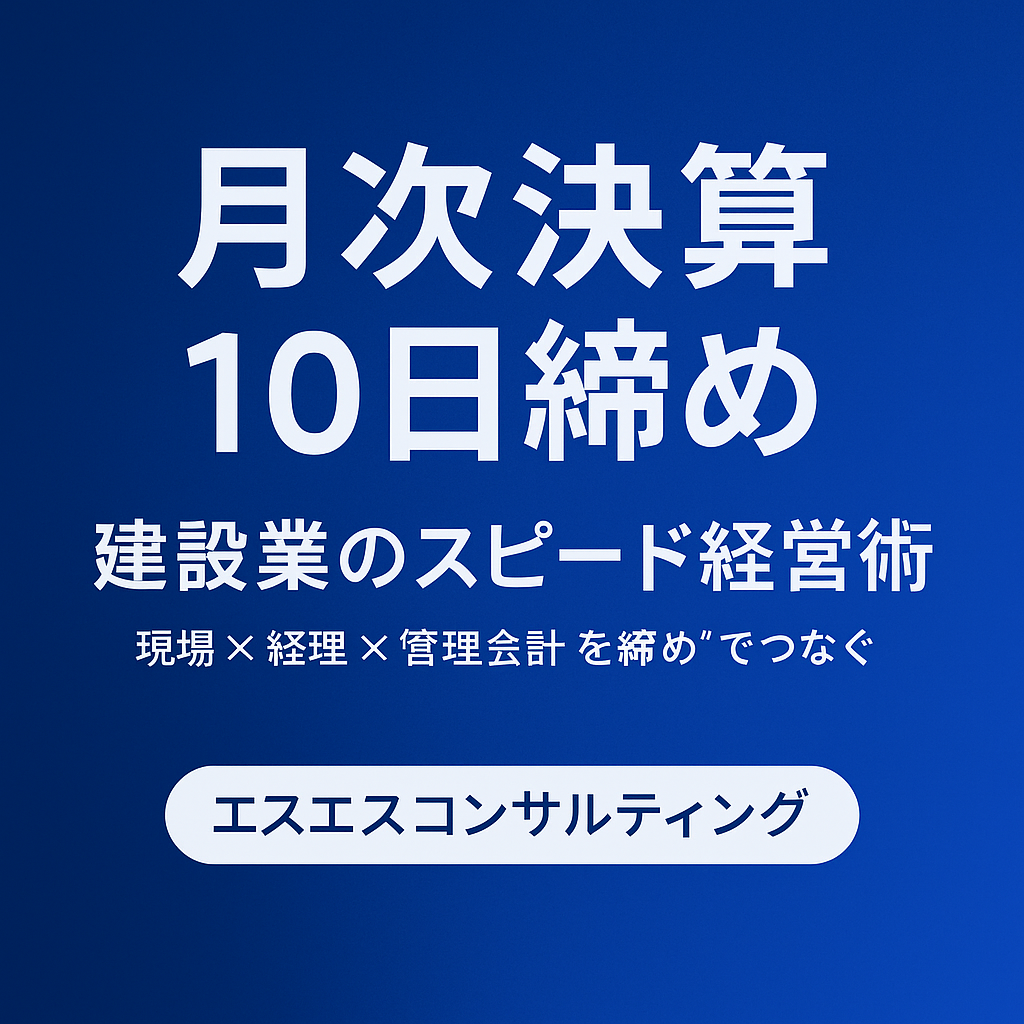
「月次決算10日締め」を実現する建設業のスピード経営術
“数字が早い会社”は強い。粗利率↑資金繰り安定銀行格付けに効く。本稿では、建設業に特有の 出来高・原価・未成工事 を10日で締め切る手順を、役割分担とテンプレートまでセットで解説します。
目次:
1. 10日締めがもたらすKPIインパクト
銀行格付け×資金繰り
- 売上・粗利の当月10日可視化で資金繰り予定精度が上がる
- 月次推移の安定化 → 信用力と交渉力(与信枠・条件)向上
現場の意思決定スピード
- 原価の異常値(外注・材工)を翌月冒頭で捕捉→早期手当て
- 未成・出来高のズレを定点観測→赤字案件の初動が速い
2. 「10日締め」カレンダー(標準フロー)
| 日付 | 主担当 | タスク | アウトプット |
|---|---|---|---|
| 1〜3日 | 現場 | 出来高の確定/写真・出来高報告アップ | 出来高報告書、出来形写真 |
| 1〜5日 | 工務 | 発注・受領・検収を締め、未検収は見積計上 | 発注明細、検収一覧、見積根拠 |
| 1〜6日 | 経理 | 仕訳取り込み・未払/未成の計上草案 | 月次試算(1次) |
| 7〜8日 | 管理会計 | 工事別粗利集計・異常値レビュー | 工事別P/L、差異分析 |
| 9日 | 経営 | 月次ミーティング(30/50万円プラン相当) | 意思決定メモ、改善アクション |
| 10日 | 経理 | 月次確定・銀行提出用レポート出力 | 確定試算、銀行向けサマリー |
ポイント:検収漏れは見積計上で前倒し。翌月差額はリバース仕訳で調整します。
3. 役割分担:現場・工務・経理の三位一体
現場(出来高・実行予算)
- 出来高の根拠(写真・出来形・数量表)を毎月1〜3日に提出
- 実行予算の更新:残工事原価の見積を毎月見直し
工務(発注・検収・外注)
- 締日を毎月末日に固定、未検収=見積計上の運用ルール
- 証憑はクラウド保管。発注番号で紐付け(例:PJ-YYYYMM-連番)
経理(仕訳・未成工事・管理会計)
- 工事台帳と会計をPJコードで1:1連動
- 未成工事支出金/出来高基準の処理を月次ポリシーで標準化
4. 原価確定の前倒し:見積計上と証憑ルール
- 見積計上の三条件:①契約or発注済、②役務提供が進行、③金額根拠が合理的
- 根拠の優先順位:見積書 > 契約単価 × 実績数量 > 過去実績の比例配賦
- 差額調整は翌月リバース。見積仕訳に出所メモ(URL/ファイルID)を必ず付記
5. 未成工事・未払の“締め連動”ルール
| 項目 | 締め基準 | 計上タイミング | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 未成工事支出金 | 出来高より未完成部分 | 毎月10日確定 | 出来高基準の一貫性 |
| 未払金(外注・材工) | 検収日ベース | 1〜5日に締め、未検収は見積 | 検収証憑の保全 |
| 前受金 | 請求・入金日 | 実入金で反映 | 工事別に債務残高管理 |
| 出来高売上 | 出来高報告確定 | 1〜3日に集約 | 写真・出来形の突合 |
6. 月次ダッシュボード(管理会計)
必須KPI
- 工事別粗利率(今月/累計/残工事見込)
- 受注残(月数換算)・出来高進捗率
- 外注依存度・労務歩掛り・材料価格差
- 営業KPI(新規元請紹介数・見積Hit率)
アウトプット(10日確定)
- 銀行向け1枚サマリー(売上・粗利・受注残)
- 赤信号案件リスト(閾値:粗利率△3pt、進捗遅延△10%)
- キャッシュギャップ早見表(入出金ズレ)
7. 10日締めチェックリスト(現場配布用)
- [ ] 1〜3日:出来高報告(数量・写真・出来形)をアップ
- [ ] 1〜5日:検収完了/未検収は見積計上根拠を添付
- [ ] 6日:工事台帳↔会計の突合(PJコード)
- [ ] 7〜8日:差異分析・赤信号案件の対処案
- [ ] 9日:月次ミーティングで意思決定→担当・期限を記録
- [ ] 10日:確定・銀行向けサマリーを生成・共有
社内規程に「見積計上」「証憑ID付記」「翌月リバース」を明文化すると運用が定着します。
8. FAQ/つまずきポイント
- Q. 未検収が多くて毎月見積ばかりになる…
- A. 原価3万以上は検収期限を月末+3日とし、工務の評価にKPI連動(未検収率)を入れて是正します。
- Q. 出来高の判断が現場でブレる
- A. 出来形写真と数量表のフォーマットを統一。差異±10%で第二承認(工務)が必須。
- Q. 10日で締めると精度が落ちない?
- A. 見積計上→翌月リバースで精度は回復。意思決定速度のメリットが上回ります。