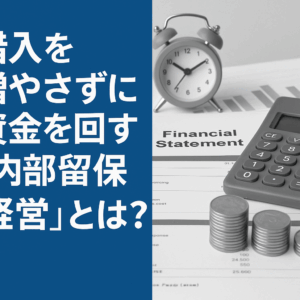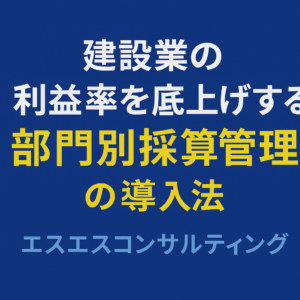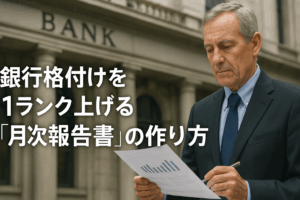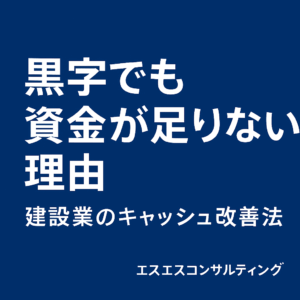「月次決算10日締め」を実現する建設業のスピード経営術
2025年10月23日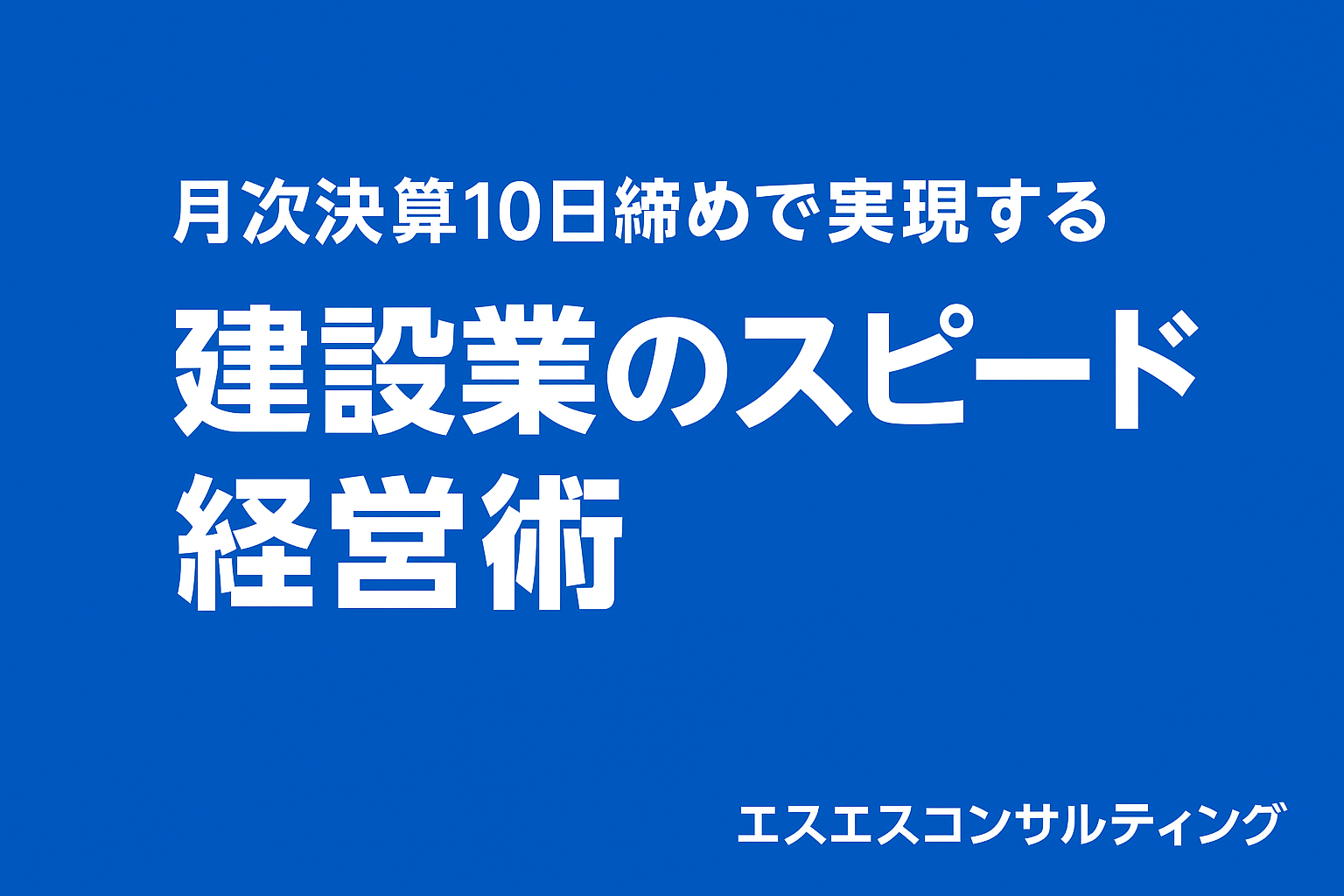
月次決算10日締めを実現する建設業のスピード経営術
多くの建設会社では「決算が出るのは翌月末」「数字が見えるのは遅れて1ヶ月後」という現実があります。
しかし、経営のスピード=決算のスピードです。
本稿では、建設業専門コンサルティングとして、月次決算10日締めを実現し、利益構造を変えた具体策を解説します。
なぜ決算が遅れるのか?
- 現場別の原価データが翌月にしか上がってこない
- 下請・外注の請求がバラバラ
- 経理担当者が現場兼務で処理が滞る
つまり、「現場→経理」間の情報伝達の遅れが最大の原因です。
10日締めを実現する3つの改革ステップ
① 現場入力の“日報デジタル化”
各現場の職長・監督がスマホから作業日報と支払い情報を即時入力。 ANDPADや建設BALANCeなどのクラウド原価管理ツールを活用することで、リアルタイムに原価が集計されます。
② 管理会計フォーマットの整備
経理が数字を「作る」だけでなく、「分析する」役割を持つ体制へ。 粗利率、原価率、労務費率を自動算出するExcelテンプレートを導入し、10日以内に利益構造を見える化します。
③ “月次10日会議”の習慣化
「データが揃うのを待つ」のではなく、「10日後に必ず経営会議を行う」文化を定着させます。 これにより、経営判断のスピードが上がり、受注・人員・資金繰りの調整が即日可能になります。
実例:ある電気工事会社の成果
| 改善前 | 改善後 |
|---|---|
| 月次決算:翌月末 | 月次決算:10日締め |
| 粗利率:20% | 粗利率:25% |
| 赤字現場の発見:平均20日遅れ | 赤字現場の発見:当月内 |
決算の早期化が、実際の利益改善に直結することが分かります。
まとめ:数字の“鮮度”が経営を変える
建設業では、「数字の遅れ」が「判断の遅れ」となり、結果として「利益の遅れ」になります。
月次決算10日締めは、単なる経理スピードではなく、“利益構造を守る防衛線”です。